 |
今回少し毛色の変った酒というと、まず「美丈夫・舞」ですが、これは栓をあけると「ポン」と吹き飛んで泡が吹き出すシャンペンのような酒。あけてすぐ飲んだときとあとで飲んだ時とでまるっきり味が違う酒です。
それから、「奥播磨」は今回「雄町」を使った酒で、いつもとはちょっと様子が違います。
東一も、今回はあえて「にごり」を選びました。 |

写真は奥播磨、「無添加直詰厳封之証」
とあります。 |
ところでお酒の量ですが、参加予定者が20人以内ということで、1800ml瓶で7本以内が適量でしょう。
しかし結果的には、飛び入りの鷹来屋を入れて9本になり、これだけでひとり4.5合の割り当てということになってしまった。
・・・そこで皆さんにお願い「この会は手酌の会です。人に注がない。自分が飲めるだけ自分で注ぐ。注いだものは必ず飲む・・」会のきまりです。
昔、ひとり5合強飲み干したことがあったけど、翌日まともに起きられた人はほとんどいなかった。
|
 |
県内の若手酒造家である浜嶋さん(写真中央)が、搾ったばかりの鷹来屋「純米吟醸」と「大吟醸」をぶら下げてはるばる緒方町からかけつけてくれました。
今年、自らの手で造りを再開して3回目の仕込みを終えほっとした表情の浜嶋さんです。持ってきてくれた2本のお酒は「純米吟醸」だけ味あわせていただき、「大吟醸」はもったいないので次回まで取っておくことにしました。
初参加の料理店経営、神河さんとも酒談義に花がさいているようです。左側佐々木さんはホテル業、いろんなジャンルの人がいるから面白い、利き酒会。 |
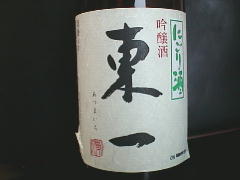 |
さて、飲み競べての感想ですが、どのお酒もそれなりにおいしかったし、レベルとしてもおしなべて高いものだったと思います。
しかし、やはり新酒としての味の硬さ・荒さの陰にそれぞれの個性が隠れてしまっている感じで、大きな違いは感じられませんでした。
もっとも、選酒の方向性そのものが一定の範囲内にあるから、当たり前といえばそれまでですが・・・
その中から、強いていえばというのがやはり「東一」、濁り酒のせいかやや甘口できわだって濃淳に感じられるのですが、明確な自己主張を持っていて好感が持てます。しかし少ししつこい味なので飲み疲れるかも・・・。
あと「山法師」とか「郷乃誉」が好ましく感じました。
|