主な山といで湯・・・記録・・・2010.1~2010.12(未定稿)
1月1日(金) 恒例の初日の出を彦岳山頂にて拝む
今年も彦岳山頂より初日の出を迎えた。例年に比べすっきりしない黎明だったが、今年を象徴するような日和にはなって欲しくないのが偽らざるところかな。
(参加者)加藤、他
今冬は例年より雪が多く、下界は桜が4~5分咲きだが山には残雪がまだちらほら。高瀬と久しぶりに英彦山に行ってみようということになり往路途中、野峠手前にある、前々から気になっていた毛谷村六助の墓を良い機会だからまず訪ねた。毛谷村六助は「太閤秀吉の前で角力をとり37人抜きをするほどの快力であった」こと、「朝鮮出兵では到る所で一番槍の功名を馳せた」らしい伝説的な人物だ。なお、彼の名を冠した焼酎が山国町の造り酒屋で売られている。なかなか味わい深い焼酎だ。胴の鳥居、奉幣殿経由で約1時間半で昼前に山頂着。約30年ぶりの山頂だ。社の日当たりのよい軒下で弁当を広げ展望を楽しみながらおにぎりをパクつく。昨日来降り積もった雪も春の陽光に照らされ、辺りに雪塊が落ちる音がする。考えてみれば、山を趣味とするわりにはこんなにゆっくりのんびりと山行を楽しむことが年に何回あるだろうか、・・・数えるほどだ。もっと地域の山に触れ合う機会を増やさねば、と思った。


毛谷村六助の墓 英彦山頂付近にて社を見上げる高瀬
(参加者)高瀬、狭間
4月17~18日(土~日) 陽春の候、久々のくじゅうに遊ぶ
加藤会長のツテでくじゅう倶楽部に宿を取り、会社の仲間と二人で牧の戸から久住山と中岳に登った。快晴の下、久住山のてっぺんからは久住高原と阿蘇、祖母~傾の眺望を欲しいままに、中岳は眼下に若葉萌えつつある坊ケ鶴を挟んで大船山から平治岳の連なり、もっと至近には三俣の山稜を臨み、春爛漫のくじゅうを堪能した。まさにこの時期、九重の山野は心地よく乾いた風が吹き渡り、大いにリフレッシュしたのだった。
ところで最近とみに身近なところでアジアを強く感じるようになった。一昨年のリーマンショック以降の景気低迷、ウォン安などで客足は少し遠のいていたが、それも昨年暮れあたりからまた戻ってきつつあるのが実感だ。「ゆふいんの森」号を毎朝、博多駅のホームで立って観ていると(かっての同僚、F島博多駅長の弁)、およそ8割が韓国人という。また同様にこの春、由布院の町を歩く観光客のおよそ8割が韓国人というじゃないか(我が旧友、G藤由布院駅長の弁)。はたまたここ数年来、天神や太宰府を歩いたら分かるが、これまた韓国語、中国語が飛びかうさまに圧倒される筈だ。で何を言いたいのかって、そぅ今回の九重登山でも下山途中、牧の戸方面からガイドに連れられ、大挙して登ってくる韓国人ハイカーに遭遇した現実を見せつけられたからなのだ。それはアジアの玄関口たる九州アイランドの住人としては歓迎すべきであって、その意味で受入れ体制をもっともっと整備すべきだし、このご時世では彼らの動向こそ、九州の経済を左右するのでは、と言っておきたい。
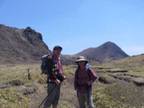



定番の西千里ガ浜から久住山 中岳の頂 星生温泉ホテルの露天風呂 くじゅう花公園はチューリップ!
さて登山を終えて宿への途中、星生温泉ホテルの展望露天風呂に初めて浸った。そしてこれがなかなかのものだったね。三俣山が眼前に迫り、白濁した硫黄泉にどっぷり捉まっては、日ごろのせわしさも忘れて時の過ぎ去るのを忘れるほど。まったくの非日常に身を置き、時の流れに任せてなかなかの山のいで湯三昧であった。
最近、仕事にかまけて山から遠ざかっている。しかし時間を作ってでも定期的に山に分け入り、能動的にリフレッシュしないといかんぞな、と強く思ったのも遠因か。その夜の宿での大宴会が盛況過ぎたのは言わずもがなだが、「過ぎたるは及ばざるが如し」もまた真理だった。しかし懲りないのもまた人の真理だからまぁ仕方あるまいて。
(コースタイム)
4/17 南福岡8:45⇒(車)⇒牧ノ戸峠
10:47 11:00→扇ケ鼻分岐 11:55→久住わかれ12:16 18→久住山12:37 13:27→中岳14:04 10→久住わかれ14:30→沓掛展望台15:19 21→牧ノ戸峠15:33 45⇒(車)⇒星生温泉ホテル(展望露天風呂入湯)15:55 16:45⇒(車)⇒くじゅう倶楽部16:50 (大宴会 泊) 星生温泉入湯(くじゅう倶楽部露天)
4/18 9:35⇒(車)⇒くじゅう花公園+クロカンコース周遊10:05 11:10⇒(車)⇒杖立温泉11:45 12:05⇒(車、日田で昼食~大分道~九州道経由)⇒南福岡14:05
(参加者)栗秋、他1名
4月25日(日) 福岡市西方、糸島半島 可也山登山と海触洞窟・芥屋の大門周遊
まどろみの朝、突然カミさんの一言で、にわかにバタバタと動き出したのが標題のアクティビティ。その訳は「糸島半島の可也山は韓国の伽耶山と因縁有りや無きや?」と自らに問い、その確認も兼ねて登りたいと申し出たのだ。発想は単純、韓国趣味が高じての発言であろうが、筆者にとっても未知の山であり、断る理由はなかった。(本文参照)




師吉登山口から可也山を望む 樹木に覆われた山頂 山頂広場から北西の幣の浜を みかん畑を下る
(コースタイム)
門司7:09⇒(車、九州道~福岡都市高速~西九州道経由))⇒可也山登山口 8:35 50→石切場 9:21 29→第一展望台9:37 39→可也山9:52→展望台9:54 10:10→登山口10:52 11:05⇒(車)⇒芥屋大門遊覧船乗り場(船周遊)11:20 12:25⇒(車、西九州道~福岡都市高速経由 途中昼食を含む)⇒薬院14:20 14:50 ⇒(車、福岡都市高速~九州道経由))⇒門司15:50
(参加者)栗秋、悦子(妻)
5月7~8日(土~日) 唐突に石見銀山&三瓶山登山一泊旅の巻
山陰で著名な山を三つ挙げるなら、先ずは日本百名山で横綱格の伯耆大山、これは言わずもがな。それに大関格で二百名山に名を連ねた東の氷ノ山、西の三瓶山がおおかたの人の認めるところだろう。その一つの三瓶山登山は食指の動くアクティビティではあるが、この山だけでは延々350㌔以上もの距離と時間を費やして行くまでのインパクトはなかった。そこに登場したのが、世界文化遺産に指定され急にメジャーになった石見銀山だったのだ。(本文参照)
(行程)
5/7門司駅8:47⇒(車)⇒中国道・吉和SA10:50 11:02⇒(車)⇒千代田JC11:30⇒(車)⇒浜田道経由・サンピコ江津道の駅12:30 13:08⇒(車)⇒石見銀山・世界遺産センター13:40 14:00⇒(バス)⇒大森14:06 15→(銀山地区~町並み地区周遊)→大森代官所跡16:27⇒(バス)⇒世界遺産センター16:36 50⇒(車)⇒三瓶温泉・さんべ荘17:30 三瓶温泉入湯(さんべ荘)
5/8 宿8:15⇒東ノ原リフト乗り場(標高570m) 8:20 24⇒(観光リフト)⇒リフト終点(標高832m) 8:33 35→女三瓶山(957m) 8:52 56→兜山(981m) 9:07 08→男三瓶山(1126m) 9:45 10:01→兜山10:30 32→女三瓶山10:44 48→リフト終点11:02 04⇒(観光リフト)⇒東ノ原リフト乗り場11:15 24⇒(車)⇒川本道の駅12:00 18⇒(車)⇒瑞穂I.C12:41⇒(車)⇒千代田JC13:00⇒(車)⇒門司15:35
総走行距離660㌔
(参加者)栗秋、悦子(妻)
5月15日(日) 出張の帰途、熊本市近郊の金峰山に登る
前々日から会社の会議などが熊本市内であり、夏に向けてそろそろ体力造りをと思っていた矢先の県外出張で、しかも金曜日とあれば当然車での参加が自由度が高い。
金峰山は、熊本県熊本市の西北、旧飽託郡河内町の地域に位置し、標高665mの一ノ岳を中心とするカルデラ式火山。熊本城天守閣から見た金峰山が、その昔、河内クロスカントリーなどの本サイト記事もあり、前から気になっていた。金峰山というと一般的には一ノ岳を指すらしいが、これを中央火口丘とする二重式火山(現在火山活動はしていない)であり、熊ノ岳(685m)や三ノ岳(681m)・荒尾山(445m)などの外輪山を含む山の総称だそうだ。山頂には展望台があり、晴れた日には有明海の湾奥、佐賀平野から島原半島、天草諸島の島影までを見渡せ、夜は熊本市街の夜景を一望することができる。山中には、巨石がいくつも横たわり宗教遺跡とみられる拝ケ石巨石群や、宮本武蔵が籠もって五輪書を書き記したことで知られる霊巌洞(岩戸観音)および五百羅漢のある雲巌禅寺、熊本から小天温泉までの旅を題材にした夏目漱石の小説「草枕」の一シーンに登場する峠の茶屋など、結構いろいろ歴史的著名人ゆかりの地なのだそうだ。
さて熊本城近くの宿を早朝に発ち、登山口・霊巌洞からのスタート。ここは河内みかんとして有名な地でもある。折しもミカンの花の甘酸っぱい香り漂うミカンの段々畑を縫うように車道を歩いた後、杉の植林の中を1時間と少々で山頂に着く。この間の、目で見、肌で感じた風景等は前述の通りだ。熊本のシンボル的な存在らしく、山頂では峠の茶屋方面からの登山者が多く、帰路に二ノ岳、三ノ岳なども勧められたが、出張疲れもあり家路を急いだ。
再就職して3年目、県外出張の機会も多く、その機会を最大限利用するとともに、在宅勤務の本来の目的を忘れていたことを思い出し、置かれた境遇を最大限活かさねばとの思いを再認識した、今回の出張山行でした。おっと!誤解されちゃあ困りますが、仕事は真面目にちゃんとやってますからご心配には及びません、念のため!


(参加者)挾間
5月22~23日(土~日) 大雨の英彦山、間隙を縫って登るの巻
会社の山岳部の大会が英彦山であり、前夜祭(青年の家泊)から参加した。総勢100名は下るまい大所帯で、かつ友好団体の韓国鉄道山岳会ご一行様10数名も加わって大賑わいのまま夜の更けるのにまかせたが、午後から降り出した雨脚はいっこうに衰える気配はなく、その点がちょっと気になった。
さて多少の二日酔いのまま朝を迎え、小降りの中、行動を開始。本来は高住神社から鬼杉コースや正面コースなど3コースに分けて英彦山を縦横無尽に歩き回る手筈だったが、足元も悪いので、奉弊殿から正面コース一本に絞り大会を行った。
で登りはそこそこの雨で良かったが、頂上に着いたとたんに大降りとなり、下りは合羽もあまり役に立たずの状況。久し振りの雨中登山はやっぱり湿っぽくていけないや。そんな中、山頂で修猷館山岳部(他の高校山岳部もいたので、高体連の大会とみた。昨日は雨の中キャンプをした模様)の面々が休憩していたので、甥の正寿のことを知っているか聞いたところ、みんな知っていたのにはちょっと驚き。二廻り近く歳は離れているも、さすが母校の後輩には知れわたっていたのだ。とまぁ間断ない雨の中、ちょっとしたエポックを紹介しておこう。下山後は英彦山温泉しゃくなげ荘で温まり生き返った。
(コースタイム)
5/22 門司駅10:59⇒(列車)⇒彦山駅13:51 14:10⇒(車)⇒英彦山青年の家14:30
5/23 宿8:25⇒(車)⇒別所8:32 38→奉幣殿8:52→英彦山(中岳) 9:50 10:16→奉幣殿11:08→別所11:27 英彦山温泉・しゃくなげ荘入湯 昼食 閉会式は宮下の公民館にて13:00 14:30⇒(車)⇒門司16:30
(参加者)栗秋、他会社の山岳部関係者大勢
5月29日(土) 40年ぶり? の別府アルプス縦走と高崎山南麓・おさるの湯入湯の巻
“おゆぴにすと”の例会(宴会)に出席するため、豊後の国へ分け入るにあたり、昼間は挾間、高瀬両兄を誘って、別府アルプスの稜線漫歩を目論んだ。しかし何故、今
別府アルプスなのかに大仰な理由はない。強いて答えるなら、日豊線で南下する度、車窓から見上げては気になっていたルートであり、筆者の記憶を辿ると、全山縦走はおよそ40年ぶりの筈。還暦を目前にして今、再びなぞることに意義を見出したのだ。(本文参照)
(コースタイム)
鶴見岳登山口(鳥居上部の駐車場・標高720m) 10:04→火男火売神社10:10 12→南平台へのコル11:08 19→西の窪11:24→稜線11:39 44→鞍ガ戸北峰12:15→舟底12:33 39→内山12:57 13:23→塚原越14:02 13→伽藍岳14:26 41→塚原温泉15:08 帰途、高崎山南麓のおさるの湯入湯
(参加者)挟間、高瀬、栗秋
6月4日(金) おらが山、霊山で北アトレーニング胎動
今夏予定の笠ヶ岳➟立山方面(またはその逆)に向けて本格的トレーニングに入った。今夏はガブリエル高瀬の「残雪の多い時期に!」との要望を受け入れ、7月下旬に入山予定としているが、具体的なコース、登山スタイル等ではかみ合わぬ部分もあり、これから詰めていく。
で、とりあえず我が家から一番近い霊山(約600m)への10kg程度の負荷での足慣らし。今後、早朝または夕方のトレーニングで徐々に負荷をかけていく予定。なんせ、最近は腰痛に悩まされ、MRI検査を受けたり治療中の身なもんで・・・どうなることやら
(参加者)挟間
6月9日(水) 北アトレーニング第二弾は本宮山へ
若気の至りで、「足も折れよ!」とばかりに安っぽい根性論を振りかざした結果が、『皇潤』のCMが気になるほど、膝痛に悩んでいる。こっちは‘エンジン’はまだまだ快調みたいだけど、ボディを支えるホイールとサスペンジョンにガタが出てきているということ。それでも、我が人生設計上、今後避けて通れないいくつかの山行がある。笠~立山・剣は残された‘大’縦走の一つであって、新穂高方面のクリヤ谷からの、笠ヶ岳山頂までの標高差2000mの登りを意識して、ボッカ力を高めつつあります昨今なのだ。つい先日までホイールの点検(MRI)と修繕を行い、どうにかホイールの調子は100パーセントじゃないけど回復。恐る恐る始めたトレーニングなので軽量の負荷。本日は早朝、本宮山(607m)を15kgの負荷でピストンした。昨年の日誌をみるとこの時期すでに25~27.5kgの負荷ですが、今年は20kg以上は持たないように決めている。それ以上持たなきゃいけないときはガブリエル高瀬に持ってもらおう。
(参加者)挟間
6月20日(日) くじゅうへ
遭難碑探索
大分合同新聞「東西南北」欄(6/17付け)で取り上げられた、くじゅうの遭難碑を風雨に打たれながら探しに行った。それは「池の小屋」より西側240m、1748.2mのピークにあり、石で出来ておりその縦1,3m横2.1m厚さ10cmの碑文を彫った碑は、台座から朽ちたかたちで前にくずれ落ちていた。80年もの長い間、風雨にさらされていたと思われ、なんと彫ってあるかが判読できなくなっていた。咄嗟に「このままではいかん、なんとかもとの姿にもどせたら」と思った次第。今年で丁度九重初遭難以来80年となるので、8月までに修復し80年の供養登山ができればと考えている。皆さんのお力添えをお願いしたい。
(参加者)加藤、他
6月22、28日 北アトレーニング第三、四弾、霊山登山
本日の朝トレは性懲りもなく、再びの霊山(600m)へ。負荷は少し増して16kg。気温と湿度が高くなった分、登りはしんどくなった。10~15kmのランニングと軽いボッカトレーニングを交互にやっているが、間に飲み会が入るので体脂肪は全然落ちない(困ったもんだ)。そんなこんなで体力の仕上がり具合はイマイチだけど、北アルプスへの想いはだんだん強くなりつつある。
(参加者)挟間
7月4日(日) くじゅうへ 遭難碑探索その2
池の小屋横の遭難碑修復のための工具、道具、資材等の検証を兼ねて、池ノ小屋へ登るべく、本山ルートの登り口の展望台駐車場まででかけたが霧と雨だ。さればと牧の戸登山口まで足をのばしたが、これまた濃い霧のなか。しばらく様子をみる間も韓国からの団体さんは重装備で元気よく登って行ったが、気は乗らず。しかたなく「東西南北」に出ていた牧の戸峠近くの遭難碑を探しに雨の中歩いた。黒岩山の途中、登山道のすぐ右脇のカヤの中に小さな石碑が立っていた。これは明らかに池の小屋の遭難碑とは違うものだ。よくもまあ間違った情報を提供したものだ。おかげでその後は久しぶりの満願寺温泉の増水した露天をたのしんだ。
(参加者)加藤
7月6日 北アトレーニング第五弾、霊山登山
北アの行程、装備・食糧などの打ち合わせとトレーニング、それに今後の登山計画に関する認識の共有化を兼ねてボッカトレーニングを行った。
(参加者)挟間、高瀬
7月10日(土) くじゅうへ
池の小屋遭難碑修復事前調査
オオヤマレンゲ鑑賞とボッカトレーニングをかねて九重遭難碑修復事前調査登山に出かけた。ボッカというほどではないけど、標高差1000m、8時間以上の歩行は、来るべき北ア行の良いトレーニングになったことは確かだ。加藤会長の、この遭難碑への思い入れにほだされての行動となったが、もともと父君の提唱による遭難碑建立・・・その剰余金によるあせび小屋建設など、因縁浅からぬものがあるのだなと、「九重山法華院物語」で知った。ところで、くだんの崩落した石板は100キロなんてものではなく、目算では1トン近くあると踏んでいる。復旧工法を考え直す必要に迫られている。



(参加者)加藤、挾間、高瀬、他2名
7月18日(日) くじゅうへ
池の小屋遭難碑石板修復作業 その1
早朝4時起きで総重量100キロの器機材のうち、狭間1往復20キロ、高瀬2往復40キロ、計60キロの荷揚げに費やした。山上での作業は、台座から三分の二がずれ落ちていた石板を2台のジャッキ、2本の角材などを駆使し、台座と平行になるまで、かさ上げしてずらした。明日は石板を起こして石塔に持たせかける作業、さらに正位置より30センチ左右にずれているので正面左側に30センチほどずらす予定。門司の方からは「登山と土木工事のコラボは新しいアウトドアの流れだ」なんて声が聞こえてきたが、そんな生やさしいものではないよ。最初は北ア遠征のトレーニングも兼ねての思いだったが、土木工事に完全に嵌りつつある。



(参加者)挾間、高瀬
7月19日(月) くじゅうへ
池の小屋遭難碑石板修復作業 その2
未明、大分市は小雨ぱらつく天気であったが、牧ノ戸に着くころには好天無風。長者原で一夜を明かした高瀬と7時に合流。すでに本日の荷揚げ分が並べられていた。パイプサポート:約10キロ弱2本、15キロ弱2本が主な荷揚げ品。本日のメンバー:前日の2人に加え、助っ人を買って出たのは狭間の義弟豊明君。彼はこの日のために登山靴まで新調して荷揚げに臨んだ。池の小屋の現場は10時から作業開始。検討の結果、難作業が予想される石板を横に30センチずらす作業は困難が予想されるため、まず最初に取り組んだ。石板は左右で厚みが違うため左右のバランスを取るのが難しい。作業中、せっかく昨日台座に水平に上げたのに、一度は失敗して基礎が崩壊したりしたものの、根気よくかつパワフルに角材を駆使してなんとか成功。



続いて、石板を起こす作業に取りかかる。約3寸厚の角材を基礎に2本のジャッキで石板を持ち上げ、左右の端にパイプサポートをかませて補強する。すべてはガブ高瀬氏の計画通りの展開だ。書けば簡単だが、2本のジャッキとパイプサポートが、常に同一負荷重であることを、総指揮官・ガブ高瀬氏がチェックしながら、それこそ一寸づりにミリ単位で上げていく。パイプサポートは約50~150センチまでの4通りを各1対用意した。ジャッキは最長20センチで伸びきるから、その都度パイプでの支えを確認しながら、角材での基礎を積み上げていく。パイプサポートというのは、ジャッキと同じような機能があるようだが、扱いには慎重さ、要領の良さとともに大変な腕力が求められる。加えて、指揮官・高瀬は極めて慎重だ。万に一つでも事故があってはならない。結構細かい注文が矢継ぎ早だ。やれ基礎が不安定だ、やれパイプの重心が外に逃げている、やれ内に入りすぎる、等々と言ってはその都度やり直しだ。ここで頼もしい助っ人・豊明君の面目躍如の場面だ。こういうことが本来好きらしく、高瀬指揮官の意図をすぐさま理解して的確に反応する。腕力も持久力も根気ある。以上の作業を繰り返して約5時間、途中のみぞれと強風、その後の照りつける太陽のもと、本日の当初予定でもある、最長パイプサポートをかませ、石板の仰角を約50度まで上げたところで、午後4時、作業終了。気になる、石板に刻まれた碑文もほぼ全容が次第に明らかになってきた。遭難者の一人「廣崎秀雄(崎は人名字体)」などの文字も明確に確認できた。直径58センチの円形の中に描かれた文字は何を意味するのだろうか、全文公開は後日のお楽しみとなった。



(参加者)挾間、高瀬、釘宮
7月24日(土) くじゅう 池の小屋遭難碑修復後の確認山行
牧ノ戸峠から池の小屋に登り、遭難碑修復後の状況確認を行った。20日、法華院山荘の皆さんの協力もあり、石板は80年前の元の位置におさまっていた。挾間個人としては7月10日本山登山道から、この遭難碑のことを初めて意識して池の小屋を目指し、4度目の山行にして80年前の姿に甦った遭難碑に接し、自分が少しでもそれに関われたこともあり感慨深いものがありました。先週、我々3名が残して帰った機器材一式のことも気になっておりましたが、碑の傍らに丁寧に置かれており、その前日の‘苦闘’に対する労いの気持ちが伝わってきました。まだ最終的な作業として接着作業などが残っておりますが、1トン近い石板なので持たせかけただけでもかなりの安定感があり、とりあえずはこのままにして近いうちに関係者による最終的な作業になりそうです。



いずれにしても本日は、この遭難碑に対する理解を参加者で共有することができ、‘今日も快調’夫人が担ぎあげたソーメンのごちそうにもあずかり、また先週の‘大分市のO夫婦’さんはじめ、新聞等で経過を知っているらしい様々な皆さんが取り囲み、池の小屋付近の小さな台地は、ちょっとした賑わいでした。下山時、‘今日も快調’さんの長男(三代目)も遅ればせながら馳せ参じ、8本のパイプサポートはじめ小道具を皆で分担して担いだことにより、荷上げの苦労も分かち合えました。さてと、管理人でもある‘こだわり’氏は、これから10日間ほど出張や北アルプス縦走などで、パソコン環境から離脱します。本日の詳報をまとめてアップしたいところですが、とりあえずサイトのトップページに今日の1枚を載せて、細かいことは後日に。
(参加者)加藤、塩月、挾間、高瀬、他3名
8月7~8日(土~日) 坊ケツルキャンプと池の小屋遭難碑にて80回忌法要(慰霊祭)を挙行
7日に坊がつる入りテント泊の後、鉾立峠から白口岳経由で池の小屋遭難碑で皆と合流する手筈で入山した。テント・食糧担いで吉部から坊がつるに入ると、のんびりのつもりがすぐに日暮れとなり、けっこう慌しかった。テントは全部で20張りくらい。前回12月にテント張った時は栗秋と二人だけだったが、夏の坊ケツルは、程よい賑わいかな。一人ビールを飲みながら、高校時代初めての坊ケツル行以来の印象深い九重行が次々と思いだされ、こういう山登りをもっとせないかん、と思った次第。こういう気持ちになったのも、先月来の遭難碑修復や、それに関わるいろいろな過去の記録など見聞きしたことによるものと思っている。これまでより九重が身近になったことは確かである。
で、昔と変わったことといえば坊ケツルに20人くらいは泊まれそう立派な避難小屋ができたことか。しかし「宿泊禁止」との看板があり、休憩場所としての位置づけらしい。鉄筋なので、むしろテントの方がいいに決まっている、と遠吠えか。8日は法華院温泉でお供物のお酒を買い、重荷(?15kgくらいか)を背負っての白口岳の急登は結構こたえた。幸い、登山道両脇の刈り払いや足場の整備など行き届いており登りやすかったが、それでも雨天時のここの下りは難儀だろうなと思った次第。で、慰霊祭については準備から取り仕切りまで大変だったと思うが、今回のことで(それに加えて昨年の星生山のこともあり)ますます九重への思いが強まったことは想像に難くないでしょう。
(参加者)加藤、塩月、挾間、高瀬、その他大勢
8月26日 黒岩岳~沓掛山
車での県外出張の帰り、ふと九重が気になり少し回り道をして牧ノ戸峠に立ち寄り、付近を散策した。
(参加者)挟間
8月28日(土) 肥前国・経ヶ岳、その予想外の峻険さを尊ぶの巻
地理的条件を理由に佐賀や長崎の山々には疎遠つづきであって、(ちょっとオーバーだけど)人生の残り時間を鑑みれば若干の焦りを抱いていた。そして図らずも会社の岳友、M木やT田両君も昨春、今春と長崎の地での勤務に身を投じたとあらば、(同行を要請するのを)躊躇しては精神衛生上よろしくなかろう、と勝手な理屈で佐賀・長崎県境に聳える多良岳~経ヶ岳山行を提案したのだった。雲仙や阿蘇よりも古い火山が連なるこの山塊は、それゆえ浸食が進み標高の割に深い森と険しい山稜を愉しめるという。加えて経ヶ岳は佐賀県の最高峰であり、これに登れば九州各県の最高峰で残すのは熊本の国見岳のみになる、と言った個人的思惑が働いたことも吐露しよう。(本文参照)
(コースタイム)
大村I.C
10:13⇒〔買物等〕⇒黒木・八丁谷林道ゲート(標高340m)
11:00 19→八丁谷登山口11:34→〔途中休憩10分〕→稜線(中山峠・標高790m)12:23 28→経ヶ岳(標高1076m)
13:01 44→つげ尾→大払谷経由〔途中休憩6分〕→黒木集落駐車場15:04 25⇒大村I.C 15:45 嬉野温泉・静雲荘入湯
(参加者)栗秋、他 会社の同好会3人
8月29日(日) 扇ヶ鼻登山
二日酔いにもめげず足慣らしに、牧ノ戸峠から扇ヶ鼻を登ってきた。山稜はすすきの穂が揺れ、いくらか秋の気配が漂い始めたところか。

(参加者)挟間
9月2日(木) 宝満山白ハケコース
宝満山というのはいろいろな登山コースがあり、様々な楽しみ方のできる山だ。今回は少しマニアックなコースをと思い、出張先での午後からの仕事の前にと、白ハケコースを選んだ。登山口を探すのに時間がかかったため途中時間切れとなり、五合目手前で引き返した。宝満山のイメージと少しかけ離れたさみしい雰囲気でこのコースは再訪する気にもなれないかもしれない。

(参加者)挟間
9月4~5日(土~日) 坊ヶツルで読書三昧
7月の、池の小屋付近にある遭難碑の修復作業や、その後の慰霊祭など、近頃何かと九重山に関わりが深くなった。その延長線上という訳でもないが、珍しく本などザックに忍ばせて雨ヶ池コースから坊ヶつるに入った。午後3時頃から夜半までテント内外で文庫本一冊読み通し、なかなかの充実感。吉村昭の「高熱隧道」に黒部への想いがますます強くなった。なお、この日のテントは25張りくらい。テント泊ではここが一番心が安らぎます。ヒーリング・マウンテニヤリング・・・これからもちょくちょく心がけたい、という心境です。
(参加者)挟間
9月8~9日(水~木) 二日連続宝満山
8日車で午後4時前に二日市入り。そのまま迷わず宝満山の登山口、竃戸神社へ。台風の影響で時おり小雨、夕暮れも早いだろうから5時になったら引き返すつもりで3時45分スタート。12kgの荷を背負ってほとんどノンストップで山頂を目指す。途中、蒸し暑さで汗が滝のごとくズボンまでびしょびしょになる。で、5時1分山頂、5時55分登山口。それにしても、このコースはほとんどが石段の大股上がり。大腿筋の良いトレーニングだ。
明けて翌9日、早朝から現地での仕事。午後までかかる予定が頑張ったおかげで11時30分に終了。それならば、と再度前日と同じコースへやはり12kg担いで。登りは前日とほぼ同じ所要時間だったが、下りは疲労からか1時間15分かかった。竃戸神社から宝満山へのルートは、たかだか標高差700メートルがけっこうしんどい。この12kgというのは、テント、寝袋、炊事道具と3泊4日のアルファ米・フリーズドライ食品と行動食、それに1.5kgの水だ。実際にザックに入っている。体力が落ちてきたので荷物のウルトラ軽量化を検討した結果、山小屋なしでも3泊4日行ける、というもの。さて、明後日は赤川から赤川~久住山~遭難碑~扇ヶ鼻~赤川だ。北アルプス第二弾、第三弾に日にちがないもんなあ(結局この第二弾、第三弾は実現しなかったが・・・)。


(参加者)挟間
9月11日(土) 初秋の九重、久し振りの赤川温泉から久住~池の小屋~扇ケ鼻を巡る
仙台に単身赴任中の鈴木君が法要で数年ぶりに帰分した。ならば夕刻に大分市内某所で旧交を温めるにあたり、おゆぴにすと三銃士は申し合わせて日中くじゅうを歩き廻ったという話。門司の住人・栗秋にとって、ただ宴会だけに大分くんだりまで行くのはもったいないので、強く働きかけた結果とも言える。
で、久々に久住高原側からの登路として赤川登山口を選んだ。初秋の涼風に浸りつつフーフー言いながら1時間40分でガスの久住山山頂へ。しかし中岳~天狗を見遣る池の小屋の丘に達するころには、秋の空が現れ、遭難碑改修にあたった御両人(挟間&高瀬) のよもやま話を聴きながらしばし山上にまどろんだ。久住分かれ~扇ケ鼻を経て赤川へ下山したが、赤川温泉は大賑わい。宿の設えやロケーションに変わりはないものの、脳裏にこびりついた「ひなびた山のいで湯のイメージ」は昔の思い出と成り果てたか。



久住山の頂にて 池の小屋遭難碑から中岳の右奥に大船山を見る 赤川温泉露天は大賑わい
(コースタイム)
4/17 大分・松ケ丘6:35⇒(車)⇒赤川登山口7:32 47→久住山9:27 46→(稲星山とのコル経由)→池の小屋10:10 12→遭難碑10:16 33→扇ケ鼻11:32 50→赤川登山口13:10 赤川温泉入湯 14:05⇒(車・竹田~犬飼経由)⇒松ケ丘15:30
(参加者)挟間、高瀬、栗秋
9月18日(土)念願の釜山・亀峰山(クボンサン)~厳光山(オムガァンサン)縦走を果たす
昨年2月、市街地に最も近く釜山港から直接見上げる亀峰山に登って、釜山北部の金井山塊踏破につづき釜山近郊の山、第二弾とした。しかしこのときは山塊の南端ピーク、亀峰山(408m)のみを登っただけで時間切れとなり、北方に構える主峰・厳光山(505m)への縦走は果たせず心残りのままであった。
しかし登山口の中央公園(チュアンコンウォン)から下山口の花村(コッマウル)まで距離にして4~5キロ、たかだか3時間程度のトレッキングであって、綿密な計画を立て用意周到に臨むような山行ではなく、「ちょっと早めに釜山に着いて、ちょびっと登ろうかねぇ」てなノリでカミさんを誘った。(本文参照)
(コースタイム)
中央洞(ホテル)11:37⇒(タクシー)⇒中央公園(亀峰山登山口)11:48 52→亀峰山12:35 55→467mピーク13:27 503.9mピーク 13:41 46→厳光山14:02 08→コッマウル(下山口)14:40 54→内院精舎(ネオンジョンサ)15:00 05→(道に迷い彷徨う)→内院精舎15:50→コッマウル16:00 15⇒(タクシー)⇒中央洞16:35
(参加者)栗秋、悦子(妻)
栂池から入り、初秋の白馬岳~雪倉岳~朝日岳を縦走し、蓮華温泉に入湯しました。ナナカマドの紅葉はまだでしたが、白馬岳の山頂から秋が次第に深まってきているなあ、という印象でした。

白馬岳山頂付近
(参加者)狭間、鈴木)
9月25日(土)久々復活の八面山アタック応援と最高点しょうけの鼻ハイクの巻
中津T.C(タートル・クラブ)が主催する恒例の自転車ヒルクライムレース、八面山アタックが11年ぶりに復活となり、挟間、豊明義兄弟コンビが出場するという。ならば応援も兼ねて久し振りに八面山登山も目論もうと思い立ったが、レース復活を知り、彼らの参加を知ったのは当日午前8時半。急遽も急遽そのものであって、にわか仕立てで門司を立った。帰途は麓の金色(かないろ)温泉に入湯。(本文参照)



ゴール地点の箭山から中津平野を見遣る 最高峰・しょうけの鼻から由布・鶴見、鹿嵐 何の変哲もないしょうけの鼻の頂
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
9月26日(日)鶴見岳西方のオアシス、南平台へ
10月の黒部へのトレーニングとして鶴見岳~南平台に加藤会長等と登りました。加藤は日本山岳会の行事の下見が主な目的。南平台でラーメンなどつくって昼食をすませたのち、しばらくのんびりくつろいだが、南平台山頂は眺めがよく広々として幕営にも十分すぎるスペース。少々ガラの悪い言葉を大声でかわしても全然大丈夫。我が会の飲み会をするにはぴったり。
で、10月には、ここで飲み会をやろうと話がまとまった(結果は掛け声だけで実現せず)。
(参加者) 加藤、挾間、他1名
10月2日(土)岩手秋田県境の和賀山塊の盟主 和賀岳(1440m)登山
快晴の下、岩手秋田県境の和賀山塊の盟主 和賀岳 1440m登山を目論んだ。かまくらで有名な秋田県横手市経由で226キロの走行。1000円高速は助かる。秋田側の真木渓谷の甘露水登山口からスタート。登山者は自分を含めて9名、岩手県側からは20数名程度でまったく静かな山行であった。岩手山、鳥海山、秋田駒ヶ岳、栗駒山、早池峰山など一望でき大満足。ちなみに秋田側の9名の内訳は山形県尾花沢から3名
川崎からの2名 千葉県柏市からの方他であった。また秋田側からの登山は2005年以来五年振り。その時は4時間2分かかったが、今回は3時間45分と少し短縮できまずまず。和賀岳にはここ3年毎年登っているが、私のお気に入りの山なのだ。また来年も行くぞ。
(参加者) 鈴木
10月11日(月)秋の平尾台、MTB&登山で縦横無尽に駆け巡るの巻
「秋の平尾台をMTBで駆け巡ろうよ」と以前から挟間兄に打診されてはいたものの、なかなかスケジュールが合わず延び延びとなっていた。そして節目の体育の日、ようやく実現の運びとなったが、思えば10年来の構想が実現した訳で、まっこと悦ばしき催事だったのだ。しかし一応地元の住人としては、事前に林道や登山道などしっかり押さえた上で、案内役に徹しなければならぬのは自明なれど、踏破済みなのは玄海T.C主催のクロカン練習会でなぞった新道寺~茶ケ床~NTT中継塔へ至る林道から貫山への登路と、吹上峠~大平山~四方台~貫山~中峠までの登山道のみ。約12平方キロにわたるカルスト台地のほんの一部に過ぎない、と今更嘆いても仕方あるまい。知っているコースをメインに辿り、余裕があれば地図と睨めっこで未知のコースを模索する作戦とした。(本文参照)
(コースタイム)
平尾台観察センター駐車場8:55⇒(byMTB)⇒茶ケ床園地9:02 05⇒(byMTB、中峠経由)⇒NTT中継塔(遊歩道終点)9:35 37→(byMTB&歩き)→575mピーク9:50 10:03→(byMTB&歩き)→貫山・四方台のコル(峠)10:10 13→貫山10:26 36→コル(峠)10:44 47→(byMTB&歩き)→NTT中継塔11:00 10→偽水晶山11:19 21→水晶山11:46 50→偽水晶山12:15 20→NTT中継塔12:28 35⇒(byMTB、中峠経由)⇒茶ケ床園地12:45 48⇒(byMTB)⇒平尾台観察センター駐車場12:53 走行(MTB&歩き)距離 約12k
(参加者)挟間、栗秋
11月3日(水)おにぎり山に登った勢いで足立山まで縦走の巻
おにぎりを持って、我が家の裏山のおにぎり山(385m)を目指した。とは言っても正味50分ほどのアルバイトで山頂に立てるぐらいの低山だが、西北側に開けた眺めは秀逸で関門海峡の船の動きが間近に見てとれ、巌流島に生息する狸のプー君の姿も望見できるのだ(ウソですよ)。 でまっすぐ往路を下山の筈が、下りはちょっと小倉寄りの別の下降コースを取ろうと言ったのが、事の始まり。小倉北区と門司区境のあてにしていた下降路は梅雨の大雨で崩壊して通行止めに。なら足立山まで行って妙見神社に降りるバイと口走ったことに、カミさんはそのボリュームを知らずに肯定したのだ。 結局、往復1時間半のハイキングの筈が、都合10キロアップダウンの激しい縦走路を4時間半かけて妙見神社に降り立ったエクササイズに。こんな筈ではなかったと這う這うの体でカミさんは訴えるも後の祭りだわね。




おにぎり山から関門海峡を臨む 大台ケ原で一休み 縦走途中から響灘を 足立山から小倉の市街
(コースタイム)
自宅10:52→(桃山登山口経由)→おにぎり山分岐11:29 30→おにぎり山11:40 12:10→大台ケ原12:25 36→吉志分岐(縦走路)13:07→足立山へ2.2k地点(縦走路)13:31 35→足立山へ0.9k地点(縦走路)14:06 08→足立山14:26 36→妙見社(下山口)15:26 33⇒(タクシー)⇒自宅15:45
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
11月23日(火)霊山トレーニング行
本日、来るべき氷ノ山行に備えて、足慣らしのためおらが山、霊山に登った。意識的に12,3キロ程度の軽い荷だが、意識的に飛ばして蕨野の集落から急坂を一気に山頂まで登った。休日ということもあり、年配登山者が多く、彼らは一様に話し好き。5月の立山を縦走したご婦人や、焼岳から日本海まで16泊で縦走したご仁も居られました。いずれも還暦をはるかに超えた皆さんで、旺盛な気力に満ちあふれていた。理屈よりも実践が大事ということか。
(参加者)挟間
11月26~28日(金~日) 初冬の氷ノ山ライトエクスペディション
かねてから鳥取・兵庫県境の氷ノ山に憧れを抱いていた。理由は二つ。一つは氷ノ山という山名にである。九州には縁の薄い氷雪の山をイメージさせるし、実際に冬季は豪雪に覆われ簡単には登れない。手強さゆえ惹かれるのは道理だ。二つ目として標高こそ1510mと平凡だが、中国地方にあっては伯耆大山に次ぐ高峰で、兵庫県最高峰のおまけ付き。もっと言えば三瓶山、上蒜山と並び日本二百名山に名を連ねているし、中国山地で伯耆大山を一人横綱とすると、西の大関・三瓶山に対し、東の大関は氷ノ山に異論はなかろう。つまり(冬季の) 難易度、品格はもちろん、横綱・大山と西の大関・三瓶に足跡を残した今、氷ノ山に食指が動くのは当然の帰結だったのだ。帰路はもう一つの目的だった、隣町(豊岡市日高町)の植村直己冒険館へ急ぎ、彼の冒険譚に思いを馳せ、志を共有し、ウエムラワールドをじっくり夢想したことも付け加えておきたい。(本文参照)




北斜面を登る 山頂台地の中央に避難小屋が 山頂にて眺望を欲しいままに
(コースタイム)
11/26~27 門司20:16⇒(車・山陽道~播但道経由)⇒養父市福定親水公園(氷ノ山登山口)2:20(仮眠)7:25→不動滝7:43 47→地蔵堂8:06 07→木地屋跡8:15 16→氷ノ山越9:02 09→仙石分岐9:45→氷ノ山10:04 57→神大ヒュッテ11:15 20→東尾根避難小屋12:08 15→東尾根登山口12:28 29→福定親水公園12:58 13
11 14⇒(車)⇒日高町・植村直己冒険館14:01 15:30⇒(車)⇒神鍋高原・大田地区15:50 神鍋温泉・ゆとろぎ館入湯 民宿森屋泊
11/28 宿8:06⇒(車・播但道~山陽道経由・門司で栗秋下車)⇒大分17:30 総走行㌔ 1160㌔(門司始終着)
(参加者) 挟間、栗秋
12月18日(土)霊山
霊山登山は、自己の体力・体調を確認するのにうってつけの山だ。これまで何十回となく登っているからだ。我が家から車で10分少々で登山口に着く。この山に登るのに特別な理由は必ずしも要らない。新しい装備など買ったらすぐに試したくなったりするときもあれば、急に思い立って登るのもこの山だ。
(参加者) 狭間
