おゆぴにすと、志々伎山と平戸・北松浦・西海を行く!
〜にわか切支丹巡礼の旅〜 栗秋和彦
○ ゴールデンウィークに動かざる者ヒトにあらず!
ゴールデンウィーク(以下、GW)後半に長崎方面の山をやろう!と豊後の国はおゆぴにすと本部から漏れ伝わってきた。どうも提案者は高瀬らしく、漏らしたのは挟間兄という図式はいつものとおり。しかし我が胸中は複雑である。骨折した右足首は半年にもなろうというのに完治には至らず、山登りに耐えられるか心もとないし、他方この時期、カレンダーどおりの休みではあるが、職責上のこともあり大手を振ってレジャー(崇高な理念を持っていても山登りも結局は遊びだわね)に生身を捧げるには、小心者としてとっても気になるのだ。しかしそれでも「GWにじっとしていてもいいのか!」との自問自答を繰り返しながら出立前夜を迎えた。まさに「ど〜ぅする、アイフル」の心境であったが、それまでメインフレームだった多良岳が、急遽、平戸島の志々伎山(しじきやま 347.2m)に変更されたとの報を受けて少し状況は変わったのだ。高瀬の思い入れが体制維持・保守派(※1)の挟間兄に優ったということかも知れぬが、「山高きが故に尊からず」であって、リハビリ修行中の我が身としては朗報に違いなかった。「うんうん行きますとも、もっと申せば行かせて下さい!」との哀願調に。後刻、カミさんの弁によれば、これで彼女のGW後半の予定があらかた決まったそうな(旦那が家にいると予定がまったく立たないらしい?)。
本隊とはJR佐世保駅で合流して取り敢えず挟間隊長(年長者を尊び)の指揮下に入ったが、「実は佐世保以遠は初めてなんだ、モジモジ...」との告白は、おおかた織り込み済みである。加えて言葉の端々から察するに予備知識もあまりなかろうと踏んだ。ならば平戸への道中、退屈しのぎに試問をいくつか用意して楽しむのも一興だ。先ずは「佐世保の街をイメージして何を連想する?」から始めたが、呼び水として筆者なら「第一は佐世保バーガーかな」と唱えたところ案の定、「何それ?」である。早速、挟間兄の怪訝そうな顔を見て楽しみつつ、{日本にハンバーガーが最初に伝来したのは1950年、佐世保だよね} 「アメリカ軍(の水兵)が持ち込んで以来、あのマクドナルド登場よりも、ずっと前から佐世保ではハンバーガーは日常食だった訳」 「しかしここ数年だよ、観光客などのクチコミでご当地・佐世保でブームとなったのは」 「今じゃ関東、関西でも佐世保バーガーの店が続々現れ、繁盛しているみたいだよ」 「佐世保バーガーの特長はとことん手作りらしく、その意味でファーストフードではなく、スローフードとして、愛されてるんだな、これが」 などと立てつづけに薀蓄を傾けると、「おぉ、それ今食いたい!」と無邪気色を全面に出したいつものおとうさんであった。
しかし何か披瀝せねばなるまい、と思ったかどうか突然、挟間兄は「村上龍は佐世保やったなぁ。知っちょるぞ!」と宣まう。なら彼の最新作で北朝鮮軍が福岡ドームを占拠して、我がニッポン国は九州割譲に追い込まれる近未来小説「半島を出よ」が巷の話題になっているが、「知っちょるよね」 「・・・・?」
作家ついでに「佐世保在住の恋愛小説の名手としての評価が高い佐藤正午は知っちょる?」 「・・・・・?」
「ジャンプ」や「永遠の1/2」などの佳作があるが、この作家は少々マニアックな存在なので万人向きではないかもしれない。「知らんでもともとバイ」 と流して端緒を切ったが、こんな風では十割ソバみたいに話の連鎖にはおぼつかず、平戸へと思いを切り替えたが、おっともっと驚いたのは平戸を島と認識していなかったことか。国定高等地図帳(高校の教科書)の縮尺で見ると、なるほど地つづきだわねと、高瀬は笑いとばしていたが、問題はもっと別のところにあると思うんだけど......。
もちろん志々伎山のこととなると、前夜までこの山の名前すら知る由もなく、「シジキサン Where?」との思いは筆者とて同じだったので、実質案内人の高瀬にゲタを預けたが、挟間兄のこだわりはたかだか標高300m余りの山を登りに、わざわざ大分くんだりから300km余り車を走らせて行くことの意義は如何に、にあったものと思う。それが冗談混じりの中にも自嘲気味に「栗ちゃんよぃ、今回は1m稼ぐのに1km走る旅だよなぁ」と宣まったことに言い表されていたのだ。
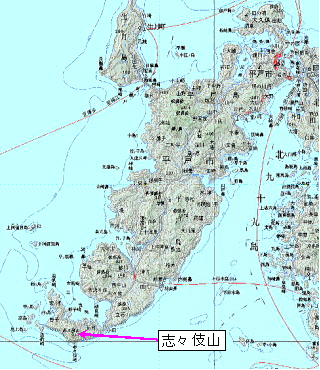
志々伎山は大分から車を走らせること300km、平戸島の南端にあり
○ あっぱれ志々伎山
高瀬の弁によると、志々伎山は「平戸のマッターホルン」と畏怖敬愛の念で言われている由、しかし登山口からの眺めは稜線からこんもり盛り上がったまさに巨大な乳首であった。登路はあらかた照葉樹林で覆われ、シイ、カシ、タブノキ、ヤブツバキと温暖な海岸線特有の森をかたちづくっているが、特筆すべきはイヌマキの巨木の迫力。9合目付近、稜線左脇にデンと居座っていたが、威風堂々としたその御姿の根元は30cmぐらいの空洞入口が開き、古木の風格を感じさせて、まるでトトロの棲家を連想させるのだ。

登山口から見た特異な山容
おっと少し話を戻すと、本来、中腹の阿弥陀寺から志々伎神社中宮経由で登るべきだったが、駐車スペースを見つけきれず、林道を詰めて標高160mの登山口まで来てしまったのだ。ここは7〜8台は駐車可能なスペースがあり、すでに稜線の末端に位置している。標高もさほどなく,序盤、山道もさほど厳しくはないと思っていたが,ロープがつけてある場所が次から次へと出てくる。もちろんロープがなくても容易に登れるが,右足に障らぬように気を遣いながらの歩きなので、特に下りには重宝した。そうか、下りのためにつけてあるんだと妙に納得した次第。

随所にかけられたロープは、実は下りのためのものだった
途中、山頂の岩峰が眼前にせまり、こんもりと盛り上がった形はとても迫力があり、期待は高まった。更にこの岩峰の南側をトラバース気味に進んでいくと、小枝の間から,五島列島が見え隠れして、意外にも近い島影に、九州本島の西外れ(この際、平戸島は本島に編入だぃ)にいることを実感するのだ。そして左に大きく曲がり、一層登りが急になると、眼下には紺碧の海,海,海。岩峰を5つほど経て山頂となったが、稜線上からの眺めは格別であった。

五島列島がかすかに遠望できる

志々伎湾を挟んで真正面、塀みたいな山容が屏風山(394m)

山頂直下最後の登り・・・左右の景色は圧巻

祠のある山頂
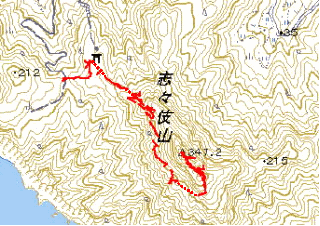
GPS軌跡による登路
(破線部分は衛生電波の捕捉が不十分な箇所であり補足した。)
○ トンビ君、名誉回復する!
閑話休題、この山旅で一番カンドーしたのはこの秀逸な景色でも、後刻巡ったカトリック教会の静謐で凛とした佇まいでもなかった。それは山頂でのトンビ君たちの華麗なるパフォーマンスだったのだ。というのも食後のデザートにイチゴを食し、何気なくまだ果肉の残ったヘタを投げ捨てたことからこのドラマは始まったのだ(地に還るという意味で環境を意識した上での行動です、念のため申し開きを!)。上空のトンビ一羽がゼロ戦の急降下爆撃の如く、そのヘタを目がけて急降下、一瞬の早業でそれを捕食し、更にはヘタの部分のみ吐き出して再び舞い上がったのだ。その瞬間三人とも「う〜ん、何ともいやはや...」と言葉を失ったね。その機敏さと雑食性、それにも増してあんな上空から我々の行動をつぶさに観察した上での予見能力とでも言うべきか、生きるための総合力に感銘したのだった。


獲物を狙うときの俊敏さに猛禽類のDNAを垣間見た
で当然、今度はイチゴの果肉部分だけちぎって上空へ放り投げると、またしてもウルトラCのファインプレーだ。これには拍手喝采するしかなかった。もちろん3度4度と繰り返し、今度は残り物の魚肉のてんぷらを放るに至っては、仲間も駆け付け上空に3.〜4羽、乱舞しつつ各々が的確に捕食するパフォーマンスを披露してくれたのだった。そこで挟間兄の「そもそもトンビはワシ、タカと同様に猛禽類の代表種だった。ところが進化の過程でトンビは種の保存のため、雑食に走ったんだ」との弁は妙に説得力があったね。なるほどワシやタカは肉食オンリーなので、生態系の変化に弱く絶滅種に指定されているものも多いが、トンビはどこでも見ることができる。歌の文句に「トンビがくるりと輪をかいた」とは上昇気流を見つけて高く舞い上がるという意味が、転じて「高見の見物」と揶揄されてきたが、真実は捕食のための高見の舞いであって、鋭い眼光、獲物を補足する俊敏性は猛禽類のDNAをしっかり引き継いでいることを、我々にキッチリと見せ付けてくれたのだ。その意味でこの日、彼らはおゆぴにすとによって名誉を回復した記念すべき日であったに違いなかろう。

中腹で唯一の展望所
○ 右折か左折か、人生の分岐点に遭遇?
下山後は

福良の海岸から仰ぎ見る山容はまさに、‘平戸のマッターホルン’そのものであった
○ 紐差(ひもさし)教会、その静ひつなロケーションの下での思索
復路、南北に細長い平戸島の中央に位置する紐差地区のランドマークは紐差教会である(とガイド高瀬の熱の入れようが伝わってくる)。ここに教会ができたのは明治18年、現在の教会は昭和4年に再建されたものである。昼間とあってミサもなく静寂の世界に包まれ、色とりどりのステンドグラスを通して差し込む光は教会内部を美しく照らし幻想的である。平戸島に住むカトリック教徒の半数はこの教会に属しているという平戸島最大の信徒をかかえる教会である。もっとも筆者は拝観途中、隣に居合わせた家族づれの一人、オレンジのカーディガンに白の綿パンがよく似合った娘? さんが気になった。服の着こなしは自然で、つんと澄ました横顔が初々しい。おっと嫁入り前の娘を思い出した訳ではないが、ふっと最近家族旅行なんぞしていないことへの郷愁に駆られたひとときであった。一方、我が隊長も教会内部の雰囲気に呑まれたのか、しおらしく静粛な面持ちを垣間見せたが、すぐに本領発揮と相成り
「おっ、お賽銭箱があるぞ、いくら入れるの?」と平気で宣まう。「ホラ、ここは神社仏閣じゃないよ、教会は献金箱だよ、声が大きいよ」 周りの観光客の含み笑いを背中に感じながら、ボクはそっとその場を離れたのだった、フーフー。


○ 懐かしの
ちょうど35年前のGW、18歳の筆者は一人西九州を旅して雨の平戸に立ち寄った。松浦資料博物館へとつづく石段をバックに撮ったセピア色の写真は青春の証として、時の流れを経て今蘇るのだ。しかしその時何に憂い、何を想ったのか、今となっては思い出す術もない。きっと青春の多感な時期、自信や不安、思い入れや葛藤、ヨロコビや悲しみなど、いろんな思いがないまぜになって我が身を旅へと誘ったに違いないのだ。そしてそれ以降、この地を踏むことはなく、久し振りの平戸詣でだったので想いは募ったが、おっちゃん二人と連れ立っての旅では感傷が介在する余地は殆どなかった。
さてこの時期、当然のことながら市街地は大勢の観光客で賑わっていたが、先ずは観光客に開放している平戸温泉、うで湯・あし湯を冷やかして、直進すると松浦資料博物館への懐かしき石段だ。しかし物見遊山な旅に博物館は似合わない。暗黙の了解事項としてパスし、高瀬の先導でうねうねと坂を上り、聖フランシスコ・ザビエル記念聖堂を目指した。そもそもこの教会は聖フランシスコ・ザビエルが平戸を訪れたことを記念して、昭和6年に建てられたもので、昭和46年(1971)、聖堂のわきにザビエル記念像が建立されたことにより、平戸カトリック教会から現在の名に改められたと言う。して見ると個人的にはその仰々しい名前に重みはなく、昔の素朴な名の方に共感を覚えるんですね。とそれはともかく、この教会は市街地から見上げる高台にあり、モスグリーンの外観、美しい尖塔と掲げられた十字架が特徴のゴチック建造物で、内部の彫刻やステンドグラスも美しいが、何と言ってもここのウリは坂道から見上げた周囲の寺院の白い壁とゴチックの聖堂風景の摩訶不思議なコラボレーションにあろう。

うんうんなんともエキゾチックで、切支丹島・平戸を象徴する景観であって、静寂さの中で映えるべきこの界隈、人の多さで若干の興ざめは否めなかったが、まぁGWのこの時期、騒々しさは年に一度の特異日の筈。全体として落ち着いたたたずまいは、小雨そぼ降るオフシーズンこそ似合うのかもしれない。
但し、我が隊長に平戸の印象を尋ねると、これらの歴史的建物や景観には興味を示さず、平戸港交流広場の近く魚介類直売所で見た牡蠣、鮑、ヒラメや青物魚にえらく食指を動かしたようで、「ここで買ってテント泊の酒宴の肴にピッタリだなぁ」、「テントを持ってこなかったのはかえすがえすも残念だったぜ」と繰り返し宣まい、その表情いっぱいに未練さが溢れていたね。もちろんテント泊、海の幸豪勢宴会を否定するものではないが、やっぱり隊長からしてこの有り様では、物見遊山の印象は拭えなかったか。
○ 露天風呂から雄大な大海原、心にしみる点景

平戸温泉と言えるかどうかはともかく・・・
しかし行き当たりばったりのこの旅、日帰りか宿を取るかまだ決めておらず落ち着かなかった。でダメ元で宿の主人へそっと聞いてみた。「まさか今日3人泊まれんでしょうねぇ」と。すると言い草がふるっていたね。「今日のような日に、空いてるところはじきつぶれますよ」としたり顔で申すのだ。う〜ん、けだし名言であって、もちろんぐうの音も出なかったぜ、悔しいけど。
○ 暮れなずむ田平教会に信仰の重さ厳粛さを見る
さて次は暮れなずむ平戸瀬戸を見下ろす丘陵地に建つ田平教会を巡ろう。高瀬がここだけは是非案内したいと申し出ただけあって、西陽がキラキラと光る平戸瀬戸を浮かび上がらせ、一服の絵を見るようにロケーションは秀逸だ。案内板によると
「明治19年(1886)出津のフランス人宣教師ド・ロ神父及び黒島のラゲ神父の勧めにより、数家族の信徒が当地に移住した。大正7年(1918)鉄川与助を棟梁として長崎教区内でも有数の調和のとれたレンガ造りの天主堂が完成し、5月14日コンパス司教によって祝別・献堂された。殉教者の血を引く信徒たちの信仰は篤く、多数の聖職者を輩出している。また外観、内部とも意匠に優れていることから平成15年に国の重要文化財に指定された」
という。ド・ロ&ラゲ神父、祝別・献堂など馴染みのない名前や言葉に戸惑いつつも、案内人・高瀬改め、ガブリエル・高瀬の真摯な説明を聞くと、この教会のただならぬ雰囲気が察せられたのだ。
で中へ入ると10名ほどが奥の祭壇でミサの真最中でした。神父が朗々と聖書の一節を読み上げ、少女(信者)が透き通った声で復唱するシーンがいつ果てるともなくつづくのだ。ミサとは神との交わりを言うそうだが、その厳粛な雰囲気にボクはいささか呑まれてしまったようだ。しかし拝観は自由なので気後れする必要はないが、厳とした静粛さは当然の定めであって最低限のマナーであろう。おっとその途中、隊長殿は退屈したのか外へ。突然「ギーギー」とドアを開け閉めする鈍い音が館内に響いたのにはマイッタね。「静かに閉めきらんの? 静粛の意味、分かってるの?」と身内としての心配、気恥ずかしさがガブリエル高瀬の表情に滲み出て、苦笑いを催させたが、当のご本人は分かっているのかしらん。


それでも筆者の耳にはいつまでもくだんの少女の祈りが残り、その信仰の重さを改めて感じ入ったが、本日3ケ所目のカトリック教会巡りで、観光地として見る教会が信仰を支える場としての教会へ、自分自身の思い入れも変わりつつあった。その意味では物見遊山な旅の途上であっても、にわか切支丹に成り済まして、この土地柄や信仰の歴史に多少なりとも思いを馳せることは有意であろう。であれば今宵は佐世保付近で必ず宿を探し、明日、西彼杵半島を南下、切支丹文学の要諦を外海の遠藤周作文学館で見出さなければならぬ。いや彼の地を見ずして帰られようかとボク自身、淡い希望がこのとき強い願望に変わったのを認めざるを得なかった。そもそもの山旅の趣がにわか切支丹巡礼の旅へと衣替えつつあったが、ただ単にガブリエル・高瀬の強い思い入れに感化されたのかも知れなかった。
○ M旅館の奇々怪々
日没と同時に佐世保着。駅構内の観光案内所は既に閉まっていたので、駅前のビジネス風のホテルを二軒直談判で当たった。がいずれもフロント付近は今宵の泊まり客であろう家族連れでごった返しており、どう見ても脈があるとは思えなんだ。「あのぅ、今日空いてませんか」と遠慮がちに伺うと、さすがに「今日のような日に、空いてるところはじきつぶれますよ」の如き、挑発的却下発言こそなかったが、躊躇なく断られたのは言うまでもない。おっと別に根に持つ訳ではないが、フロント嬢の表情は「こんな日に空いてる訳ないでしょ」がアリアリと見えていたね。おっと恨みつらみの類はもう止めよう。
で意気消沈しつつ、三軒目を訪ねようと、広場を挟んで真向かいの
△×シティホテル方面へ移動中、フト傍らを見遣ると昔ながらの立て込んだ商店街の一角に、木造三階建てのM旅館を認めたのだ。「おっちゃん、あそこを当たろう」と即交渉。結果は○だったが、70歳を越えているとおぼしき女将さんは我々の風采をしげしげと見ながら値踏みの様子。そして何やら「あの部屋のお客さんをこっちに移ってもらってブツブツ....」とひとりごちて、しばし思案の末に「分かりました、何とかしましょう」とのご宣託。如何にももったいぶった仕草であったが、この際、鳴く子と地頭と女将さんには逆らえぬ。ありがたさを表情に滲ませて軍門に下った?のだった。が、まさにフーテンの寅さんが好むような、ミシミシと老朽木造特有の擬音を発するいにしえの宿であったね。とそれはともかく三階に通された我々は一部屋でいいのに二部屋あてがわれ、ちょっとビックリ。そして後刻、外での夕食大宴会を二次会まできっちりとこなして帰還しても、隣の部屋に人の気配はなく、つまりお客さんでいっぱいな風には見えなかったのだ。くだんの温泉宿の主人の言を信ずれば、(経営上)先行き不透明な宿となろうが、まさに奇々怪々な旅篭であったね。まぁしかしこの宿の名誉のために申し添えれば、朝までぐっすりと眠れてすっきりした目覚めをもたらしてくれたが、つらつら考えるに薄っぺらな布団に駅前の騒々しさは、我家の住環境によく似ていたからとハタと気づいたのだった。
○ 虚空蔵山に登る
肥前国のマッターホルンと云えば2年前に登った(ばかりの)


ところですぐ近くには高さ15mほどの立派な展望台があり、ここに立つと五島列島や佐世保を一望するワイドなパノラマが広がり、それなりにこの山、いやこの構造物の価値が分かろうというもの。がこの秀逸なるロケーションなら、時刻を変えて五島列島に沈む夕日、佐世保やハウステンボスの夜景などを見るには一級の展望所となり得るのではないか。その意味では、この山の価値は展望台に有り、と結論付けてそそくさと下山の途についたのだった。(やっぱり山は自分の足で登らなアカンと、お二人の表情は物語っていたね)
○
さてこの旅のゴールは
もちろん彼の代表作、『沈黙』は、この地が舞台の一つであり、切支丹禁制下の17世紀、潜入した宣教師と日本人信者の心の葛藤、弾圧哀史を綴ったものぐらいの茫漠とした認識はあったが、むしろ彼がこの地を舞台に書かなければならなかった理由、或いはタイトルの「沈黙」とは何を表すのか、などなど疑問を解明するためのキッカケとして、この地、この文学館を訪ねたかったのだ。そしてその呼び水は図らずも平戸島や北松浦・
おっと先ずは外海の地勢はと言えば、角力灘に面した入り江と、それを囲むように広がる集落。一見、何の変哲もない浦に見えるが、高台には赤レンガの教会や十字架を掲げた墓地が海を見下ろす。この外海をはじめ、五島列島や生月島などは「隠れ切支丹」の里としてつとに有名だが、藩政時代の過酷な迫害にもかかわらず、およそ250年にわたって、密かに信仰を守り続けてきたその頑ななひたむきさ、意志の強さが、すごいのだ。
今でもこれらの浦々にはキリスト教徒が多く、中には、禁教時代に変容した信仰を頑なに守り続ける人々もいると聞く。長崎の西に広がる海は、そんな信仰の重さを呑み込んで現在に至っているのだ。
さてこの出津地区には前出のド・ロ神父(※4)が力を尽くし、この町を支えた証である出津教会やゆかりの文化的施設が点在して、その歴史を今に伝えている。そしてその入口の歴史民俗資料館の側に車を置くと、その傍らに海を見晴らして、一つの文学碑が立つ。『人間がこんなに哀しいのに、主よ海があまりに碧いのです』 と、言わずと知れた『沈黙』の一節が刻まれた碑であるが、その真向かい小高い丘に、文学館を仰ぎ見るという構図は、はやる心を益々助長させるのだ。



そこで、ひとまず『沈黙』のストーリーをおさらいして臨場感に浸るのも一興か。何を隠そう、この旅を終えるや否や、文庫本を買い求め二日後には読了した身だから、まだ記憶は鮮明なのだ。
キリシタン弾圧下の十七世紀、ポルトガル人宣教師ロドリゴは、ひそかに九州に上陸、隠れキリシタンへの布教を続けるが、行を共にして来たキチジローの裏切りで捕らえられる。棄教を迫る役人に屈しなかったロドリゴも、穴吊りにされた信者たちの命を救うために、とうとう踏絵に足をかける。クライマックスはその時聴こえて来た神の声、すなわち
「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている」 のくだりであろう。

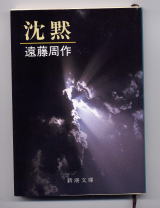
ロドリゴ自身の心の中のキリストの声だったとも読めるが、作品発表後、この人間の弱さを肯定するキリスト像(観)は、大きな反響を呼び、教会の一部からの激しい批判などもあったと記されている。それほど重いテーマとして書き進めたのは、たまたま訪れた
その意味では低山彷徨日帰り紀行の筈が、一泊二日行ったり来たり、にわか切支丹巡礼の旅に様変わりはしたものの、日常では得がたい見聞を広げて、なかなか充実した二日間だったと結論づけたい。おっと、「論点定まらず、まったくの冗長だぜ!」との編集長の声が聞こえてきそうだが、神の声とは違い、聞き流しても罰はあたるまい。
(※1)多良岳は九州百名山のひとつであり、肥前国の山を語るに、この山抜きには語れない。人気、標高、歴史等どれをとっても保守本流であろう。
(※2)ネットで調べたら、「
(※3)平成の大合併で昨年、西彼杵郡から
(※4)明治12年(1879)、外海地方の主任司祭としてフランスから赴任。当時、困窮を極めた暮らしをていた外海の
人々を魂と肉体の両面から救い、生涯の全てを彼等に捧げた。何より建築、製粉、搾油、パン、マカロニなどの製
法、農機具、イワシ網工場などなど、あらゆる知識と能力を駆使して暮らしぶりの向上に努めた。宣教師とは祖国
のプロパガンダ要員とのうがった見方をしていたが、少し考え方を変えねばならぬか。
(行程)
5/3 ①挟間&高瀬 大分6:02→(車)→JR佐世保駅→9:15 ②栗秋 博多7:37→(列車)→JR佐世保駅9:22 ①②合流後出立9:27→(車)→平戸大橋10:34→(車)→
5/4 佐世保7:53→(車)→西海橋8:25 30→(車)→虚空蔵山8:50 9:00→(車)→道の駅・西海9:05 20→(車)→外海地区・出津文化村(ド・ロ神父記念館〜出津教会〜遠藤周作文学館〜黒崎教会)10:00 12:00→(車)→JR諫早駅12:45 昼食後①②解散 ①挟間&高瀬 諫早駅13:30→(車)→大分17:00 ②栗秋 諫早駅13:48→(列車)→博多15:18
Photo by Hasama & Kuriaki, Map by Hasama