主な山といで湯・・・記録・・・2008.1〜2008.12(未定稿)
1月1日(火) 初日の出を拝みに彦岳へ
恒例の初日の出登山、今年は佐伯湾を臨む彦岳を目指した。
(参加者)加藤、他
1月13〜15日(日〜火) 今年の干支の山、三重県の子ノ泊山登山
今年の干支である子ノ泊山(906.7m 三重県紀宝町)に登ってきた。13日朝 大阪南港着 同期の岳友 佐藤君の出迎えをうけ、奥さんと大分からの3人(私 西 生野)で佐藤君の愛車にて一路南下 和歌山ー田辺ー白浜にて観光 串本へ本州最南端をみて那智へ。那智本宮、那智の滝をみて今日の宿「くまのじ」へ。夜 6寺より80人の大宴会 1年に1度しかあえない山の友人達と旧交をあたためて飲めや歌えの大宴会。14日快晴 車にて登山口に移動の後Aコースの急登コースでヤケくらをへて2時間30分で山頂へ。万歳や慶祝の行事に約百人参加。地元の新宮山彦グループの豚汁やコーヒーの暖かい接待をうけ、楽しい一時。 好天にめぐまれて眺望のよい山頂であった。下山後 大分4人と佐藤夫妻で西日本一の大露天風呂のある渡瀬温泉にてもう一泊。15日は 熊野古道 伏拝王子まで歩き 八ッ瀬の吊り橋を渡り 大阪に出て 15時51分新大阪発の新幹線に乗り大分着 19時48分の旅であった。 お世話になった佐藤君に感謝です。また来年 牛のつく山で再会を。」
(写真左から、ヤケくらコースの登り、子の泊山 、山頂にて、西日本一の大露天風呂 渡瀬温泉)




(参加者)加藤、他4名
1月13日(日) 今年の初湯は久し振りの玖珠・椿温泉へ
年末年始は仕事上、待機を余儀なくされたので(5日夕刻は禁を破って?大分へ新年会に行ったけど...)、今週末を利用して田舎へ年始挨拶の小旅行を企てた。で昨夕、馴染みの玖珠・椿温泉にて1時間半にもおよぶ湯浴み三昧。つまりまったりと湯に入ったり出たりを繰り返しながら、世俗のしがらみを忘れ、頭をカラッポにして寿命を延ばした次第。いつもながら誰一人おらず、ドゥドゥと流れ入る高温かけ流しの湯を独り占めするこのシチュエーションが尊い。あぁ願わくば長逗留を決め込みたいところだが、こんな一日だけの刹那的入湯だからこそ、我が錆びかかった湯への渇望を磨いて?くれるのかなぁ、とも思いまする。
(参加者)栗秋、悦子(妻)
3月21〜22日(金〜土) 九重の山々に春をつげる法華院温泉の開山祭に出席
快晴の星生山に登り、法華院へと下った。まだ日陰には雪が残っており、早春の風情。翌22日は法華院温泉の広場でおこなわれた開山祭に出席した。今年の山の安全を祈願して焚いた護摩の煙が、早春の山々をバックにゆらゆらと昇っていく様は、ようやく九重の山々に春を告げる風物詩なのだ。写真左は星生山から久住山を、右は護摩焚の様子。


(参加者)加藤、他
3月22日(土) 春色にわかに満ちて、唐突に下関・竜王山に登るの巻
春色にわかに満ちた彼岸の候、ポッカリと空いた午後のひととき、思い立って下関の竜王山(614m)を目指した。この山は大陸から響灘を渡ってきた空気が日本に来て最初にぶつかる山なので、雨雲が発生しやすく、昔から雨乞いの神事が行なわれてきたという。竜は雨をもたらす存在とされているから、山名の由来はこの辺にありそうだ。その山頂からは360度のパノラマが楽しめ、西方直下に響灘、南方は少し離れて関門海峡などの海を押さえ、すこぶる眺望に秀でているという。それゆえ古くから水の神として雨乞い、海上安全、大漁祈願の神として崇められてきたのであろう。そういった地元の民の愛着が歴史を作り、重量感のある山容と相俟って、登高意欲をそそるのだ。
そして下山後は登山口から県道244号を北へ(車で)3分の吉見温泉に10年振りに立ち寄ったが、相変わらず田舎の鄙びたいで湯の風情が懐かしく、肌にまとわりついて離れないアルカリ性単純泉の感触は山里のいで湯によく似合のだ。(本文参照)
(コースタイム)
門司13:10⇒(車)⇒吉見下(県道244号)登山口14:10 19→上宮の鳥居14:56 15:00→竜王山15:26 45→上宮16:07 10→吉見下登山口16:36 42⇒(車)⇒吉見温泉16:45(入湯)17:35⇒(車)⇒門司18:40
(参加者) 栗秋
4月12日(土) 荻岳
週末、出張の機会を利用して荻岳にちょこっと登ってきた。いつもは緑に覆われた山肌だが、野焼き直後で黒々とした地肌むきだし。それでも、ワラビ、タラノメなどがそろそろ動き始めていた。この山は宮崎県五ヶ所の三秀台とともに、九重、阿蘇、祖母の眺めの大変良い場所だが、あいにく遠望されたのはご覧の通り春霞で薄ぼんやりとした輪郭のみで、ちょっと残念だった。写真は左から、阿蘇根子岳高岳、祖母山、荻岳山頂付近。



(参加者) 挾間
4月26〜27日(土〜日) 九重・泉水山〜黒岩山縦走 小雨烈風のち快晴春暖の山旅
会社の山仲間と九重の一角をちょっとだけ登り、夜は麓の湯宿で一泊大宴会をやろうということになった。山登りのパートのみ遠慮がちにちょっとだけと銘打ったのは、決してへりくだった謂いではなく、ホントにちょこっと山に登って、エネルギーの大半は湯煙一泊大宴会につぎ込もうと目論む我がメンバー諸兄の思惑によったが、せめて実働4時間ぐらいは山歩きに充てないと、宴席の酒も美味くはなかろうとおもんばかる訳ですね。
そこで長者原を起点&終点に下泉水山〜上泉水山〜黒岩山〜牧ノ戸峠経由で自然歩道を長者原へ帰るコースを採り、勇躍勇んで出立したのだった。時間はたっぷりあったので、下山途中に牧の戸温泉・九重観光ホテルに入湯、硫黄泉たっぷりのこの湯殿、湯舟から視界いっぱいに広がる眺望がここのウリであって、筆者にとって実に24年ぶり ノスタルジア溢れる再入湯であった。また一夜の宿となる、くじゅう倶楽部備え付けの星生温泉・露天にもしっかりと入ったのは言うまでもない。(本文参照)
(コースタイム)
長者原10:38→樹林帯分岐11:10 15→下泉水山11:23 26→上泉水山11:53 57→黒岩山12:35 13:00→牧ノ戸峠13:20→(九州自然歩道経由・途中昼食13:33 14:10)→牧ノ戸温泉入湯(九重観光ホテル)14:25 15:53→長者原16:10 星生温泉・くじゅう倶楽部泊
(参加者) 栗秋、伊藤、他2名
4月28日(月) 残雪の伯耆大山登山
4月25日〜29日までの5日間、仕事で松江に滞在。28日に残雪の伯耆大山に登った。33年ぶりのこととて、登山口には良く整備された無料駐車場があった。弥山までは2時間半の行程だが、夏道四合目辺りは、まだ樹木は芽吹いておらず、北壁も見通しよく眺められた。稜線上の突起はユートピア小屋。六合目を過ぎると残雪に悪戦苦闘した。別山沢上部辺りからは、北壁が圧巻。行者谷方面にはシュプールもあったが、登山者は‘時ならぬ’残雪に(大山ではこの時期当たり前?)、うれしさ半分、怖さ半分といったところだろうか。そして九合目辺りからは木道を行くことになる。時折、幅広い雪原を横切るが、サングラスがないと雪盲になりそうなほど、春の陽射しが照りつけました。登山口から2時間半ほどで山頂。といっても最高点・剣ヶ峰はその向こう。崩壊が激しく一般登山者はこのちょっと先まで。





(参加者) 挾間、恵子(妻)
5月4日(日) 新百姓山〜桧山縦走
祖母傾山系の新百姓山(1272m)から桧山.(1297m)に至る稜線上のアケボノツツジを愛でる目的で縦走した。この付近では盛りは過ぎてはいたものの、充分味わうことができた。一方、シャクナゲは開花始めであり、来週以降が見頃となろう。写真右は、祖母傾山系の新百姓山(1272m)に至る稜線上のブナの巨木。周囲6,7mはあろうか?圧巻。



(参加者) 挾間
5月15日(木) 新緑の由布岳山麓を歩く
猪瀬戸から飯盛ヶ城まで新緑の由布岳山麓を歩いた。登りはじめは石ころゴロゴロだが、空気がおいしく、鳥のさえずりも賑やか。登山口には車が結構停まっていたが、多くは、猪瀬戸からの由布山頂が目的のようだ。この時期、山麓はまさに‘新緑’に覆われ、時折木洩れ日が差す、といった具合。木々の間から目的の最初の山・日向岳を垣間見る。日向岳の山頂付近では、思いがけずもサクラソウの小さな群生に出会い、心和むものがあった。ここまでのコースの大半は鬱蒼とした森の中だが、日向岳からの下りでこのコース中、唯一、由布岳の山頂が拝めるスポットがあり、ちょっとした感動。そして正面登山口方面に回り込むほどに、由布山麓の裾野は明るい樹林帯に変わり、同じ新緑でも緑の色合いは微妙に変化しているのが分かった。飯盛ヶ城の登りではエヒメアヤメ二輪とミヤマキリシマ一輪に疲れが癒されたが、正面登山口から飯盛ヶ城に直接登る登山道が最近整備されていることを初めて知った次第。




(参加者) 挾間
5月17日(土) 新緑に目は沁みつつの戸の上山
朝日は我が裏山(門司アルプス)をバックライトの如く、神々しく浮かび上がらせ、陽が高くなるにつれ緑々に磨きがかかり、その度合いを増して我を誘う。
という訳でみずみずしい午前のひととき、久し振りに戸の上山(518m)登山を思い立った。が、どうせカミさんは同意すまい、と義理立てのつもりで声をかけたところ、「うん、行ってもいいよ」と意外な反応。これにはちょっと驚きもしたが、もちろん揶揄することも筈もなく、十数年ぶりの同伴登山となった。(本文参照)
(コースタイム) 自宅9:36→桃山登山口9:52→大台ケ原10:20 24→戸の上山10:46 59→大台ケ原11:22→登山口11:48→自宅12:08
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
6月7〜8日(土〜日)おゆぴにすとの集いinくじゅう倶楽部
挾間会員の退職慰労会という名目ではあったようだけど、実質的な発起人の松田会員が長引く母君の看病・介護のため出席できず、結局段取りの大半は慰労される筈の挾間会員がやることになった(いつもながら御苦労!)。
宴は吉賀会員の尺八披露に始まった。尺八といえば都山流、都山流といえば登高会往年の‘カリスマ’N氏が想起される。話題は当然昭和40年代後半にタイムスリップ。次第にエスカレートし、登高会会員のなれの果ての近況と登山感の開陳に至り、ついには侃々諤々、いや酩酊度も高まり喧々囂々というべきか、若干名の議論がとどまるところを知らず。議論に圧倒された還暦組は早々に別室にあるいはタヌキ寝入りを決め込む者も・・・。結論としては表現方法の違いこそあれ、山への情熱は皆持ち続けているということにしておこう。もちろん朝な夕なくじゅう倶楽部備え付けの星生温泉・露天にもしっかりと浸かり、おゆぴにすととしての責務の一端を果たした?(山に登らんでよく言うよなぁ)
(参加者) 加藤、内田、吉賀、塩月、狭間、高瀬、栗秋
6月21日(土) 大雨で心、いで湯に在らず!とも高崎山温泉・おさるの湯にちょっと浸る
梅雨空の下、宮崎出張の帰り、久し振りに大分駅に下り立った。それにしても今年の梅雨はよく降る。加えてピンポイントのゲリラ的降雨傾向が顕著とあって、宮崎は曇天なれど青空も垣間見れて心穏やかであったが、宗太郎峠あたりからポツポツと。更に佐志生から幸崎への峠を越えると本降りの様相を呈してきた。
しかしまだまだ梅雨の風情を愉しもうと余裕は大有り。そこで出迎えた挾間兄、それにひょんなことからバッタリ逢った加藤御大と三人で大分市近郊
(正確には由布市挾間町) の高崎山温泉・おさるの湯を目指した。
もちろん初見参の湯だが、山の中の一軒屋 (とは言うものの大分道の縁に有り、車の走行音がわずかに聞き取れる) でロケーションは秀逸の筈。真近に仰ぎ見るべき高崎山も、見下ろすと緑々の山野が広がる眺望も雨に煙って茫々の感。ならばコーラ色のアルカリ性単純泉にゆったりと身を任せることだけを念頭に浸ったつもりだったが、だんだんと雨脚が強くなり、露天の軒先を叩く雨音も激しくなると、商売柄落ち着かなくなるのは悲しい性か。一日も早く梅雨が明けることを願うばかりなり。


(参加者) 加藤、挾間、栗秋
6月28日(土) 祖母山メンノツラ谷遡行
ひこさんクラブの精鋭が、今年は祖母山系のオオヤマレンゲを訪ねるという。南アのトレーニングの一環として飛び入り参加した。梅雨前線の真っ直中にもかかわらず、よりによって谷筋からのアプローチ。雨中、約4時間半の悪戦苦闘の後‘貴婦人’に巡り会うことができた。写真左と中央:オオヤマレンゲを求めて、祖母山系メンノツラ谷を遡る中高年登山隊総勢5名。右:九合目付近で‘貴婦人’を発見。



(参加者) 加藤、挾間、他
7月6日(日) 鶴見山登山
梅雨明けを思わせる暑さの中、踊石からのコースで久しぶりに鶴見岳に登った。前日、炎天下のボッカトレーニングがたたってか、足取りは重かった。雨上がりとあって、山頂付近からは九重、祖母傾の連嶺を見通しつつ、帰路は南平台に回った。南平台は未踏の頂だが、秋の楽しみにとっておこうと、あえて山頂直下を素通りした。最後までかったるい足取りだった。写真左:城ヶ岳の向こうに九重連峰を望む、右:遙に祖母傾連峰を望む。


(参加者) 挾間
7月6日(日) 三俣山登山
三俣山の山頂より大分地方の梅雨明けを見届けた。午前中は山の上部にガスもかかり風もつよくよくなかった天候も12時すぎたころからだんだんと好転のきざしがみえお鉢めぐって山頂にもどったころには、遠くの英彦山もくっきりと見えてきて、まさに梅雨が明けた瞬間に立ち会ったという心境であった。
(参加者) 加藤、他
7月6日(日) 玉石混交隊、盛夏涼風の涌蓋山に登るの巻
かっての会社の同期で岳友、今はさいたま市在住の医師、H島君と九重は涌蓋山を登ろうということになった。5日九州入りし、早々と背振山に登った後は佐賀での同窓会に出席して、翌6日(本日)からが本命、本番。つまり8日まで休みを確保して九州の山々を積極的に登ろうという算段である。そしてその初日を筆者の案内で涌蓋山に充てた訳だが、20数年前、涌蓋越付近まで到達しながら風雨で登頂を断念して以来、思いを寄せていた山とのこと。う〜ん、そんなことなら一肌も二肌も脱がねばならぬが、どうせなら会社の同僚T田君やM木君も引き連れてワイワイガヤガヤ登山も面白かろうと踏んだ。(本文参照)
(コースタイム)ひぜん湯登山口10:43→涌蓋越(林道出合)11:39 48→女岳12:10 15→涌蓋山12:25 13:22→(往路を戻る)→涌蓋越13:50→登山口14:36 下山後は川底温泉せせらぎの湯入湯
(参加者) 栗秋、他3名
7月17〜18日(火〜水) 北八ケ岳&車山(美ケ原)彷徨
蓼科温泉にある会社の保養所をベースに、北八ヶ岳と車山(美ヶ原)に家内と行ってきた。八分咲きのニッコウキスゲと、中央線電車・帰りの車窓から仰ぎ見た、移りゆく甲斐駒ヶ岳の雄姿(写真下)が印象的だった。




(参加者) 挾間、恵子(妻)
8月3日(日) 門司アルプスの難峰?おにぎり山攻略の記
我が家の背後に聳える“さんかく山(仮称)”を攻めようと企てた。何せ原生林に覆われた標高385mのこの山、知り得たかぎりでは明瞭な登路がなく、一部始終藪漕ぎが想定され、たおやかな門司アルプスの稜線上(ちょっと外れるが)にあっても難峰に違わぬ存在感を漂わせている。ましてこの盛夏、酷暑、雑草繁茂のこの時期に敢えて決行することの意義は、何だ!と大上段に構えるつもりはさらさらないが、いつも間近に仰ぎ見るこの峰に早晩登らなければとの思いは、一昨年この地に転居して以来、つのるばかりであった。加えて盛夏ゆえ下山後のビールの美味さは如何ほどか、決断を後押しした大きな要素だったが、まぁ我ながら単純人生の処し方に苦笑するのみである。で門司の住人、K子兄を誘って挑んだ結果は桃山コースの稜線手前から右上へ踏跡があり、小さな案内板もあって、なんなく頂に到達。山名標には「おにぎり山」とユーモラスな名が授けられていた。(本文参照)
(コースタイム)自宅15:58→(桃山登山口経由)→稜線(縦走路)16:36 42→(稜線からの登路を探すも断念)稜線(縦走路)16:47→おにぎり山登山口16:51→おにぎり山17:01 12→桃山登山口上部の砂防ダム堰堤17:34→自宅18:00
(参加者) 栗秋、他1名
8月8〜16日(金〜土) 南アルプス光岳〜三伏峠縦走
何か書いて
(参加者) 挾間、高瀬、鈴木
9月12〜13日(金〜土) 久々の釜山一泊、金井山塊に足跡を残すの巻
仲秋の候、一泊でカミさんと韓国・釜山を旅した。一週間前に急遽思い立ったこの“海外旅行”、幸いにも今年は一度も台風に見舞われず、我が商売にとっては悦ばしいかぎり。しかも長月に入っても天気図にはその卵も見受けられなかった。ならばこの隙にと、釜山詣でを計画し、釜山アルプスの金井山(クムジョンサン) 縦走と下山後の東莱(ドンネ)温泉を組み入れて、長年の懸案事項を果たそうと目論んだが、結果は如何に?(本文参照)
(金井山トレッキング コースタイム)
9/13 金剛公園正門8:22→公園内山麓駅8:30 50⇒(ロープウェイ)⇒山上駅8:58→南門9:17 21→東門9:58 10:03→展望ポイント10:32 44→東門11:08→山城村11:20
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
9月15日(月) 伊吹山登山
9月14日 大津市で行われた日本男声合唱協会第19回演奏会に南蛮コールの一員として参加。600名の仲間達と歌い、翌15日に伊吹山に登った。大津を朝のJRで同じ団員のN氏と発ち、近江長岡にて岐阜からきた友人O氏と合流し3人でタクシーにて登山口へ。ここからやく3時間の登りで山頂へ。花の時期からはややはずれてはいたが、それでもサラシナショウマ、タムラソウ、イブキトリカブト、イブキフウロウなどなど、さすがに花の豊かさを誇る山であった。山頂には深田久弥にして言わしめた「お気の毒なくらいみっともない」作りのヤマトタケルの石像がたっていて、ドライブウエイを利用してきている観光客でいっぱい。あいにくの天候で眺望はきかなかったが、なんとか下山するまで降られなくてすんだ。また花のよい時期に再訪をと思う山であった。



(参加者) 加藤、他2名
9月21日(日)背振山&鏡山登山
唐津方面に出張する機会があり、移動日を利用してマイカーにマウンテンバイクを積み込んで、背振山と栗秋会員お薦めの鏡山に登った。どちらの山もマウンテンバイクを漕いでの‘登山’ということでひと味違った景色を楽しむことができた。左:背振山、右:鏡山山頂にて。・・・ところで「ちゃんと仕事はしとるんかいな?」との疑問については、言わずもがな!翌22日は早朝から頑張り、夕方は佐賀市内に移動して夜遅くまで。翌23日は大分への移動のみなので、さらに背振山系奥深くと思いましたが、前日の疲れがとれず、断念した。後で考えたら、折角の祭日なのにちょっともったいなかったな。


(参加者) 挾間
9月23日(火) 福岡市の展望台、立花山登山と千早温泉・極楽湯入湯
長月も下旬、秋分の日を迎えても残暑はしぶとく残る。あぁ、秋の爽やかな風を受けて軽やかにエクササイズとはいかないものか。で唐突に思い付いたのが往復電車を使ってのエコトレッキング。下山後に温泉でも浸ってビールなんぞ飲めれば、軽やかとはいかずともエコロジーを味方に付けただけ、多少の享楽些事は許されよう。ならばと物色したのが、かねてより気になっていた福岡市街を展望する立花山だ。福岡市東区、新宮町、久山町の境界に位置するこの山は、古くから海路、陸路の目印とされ、万葉集にも登場?する由緒正しき名山だし、鎌倉時代末期の築城から戦国末期の廃城まで、博多の町や筑前国の変遷を見つづけてきたこの山の歴史の一端を肌で感じたいとの思いが募った。
下山後は千早の極楽湯(れっきとした温泉なのだ!)へ直行して、小ぶりながらも山といで湯を堪能したのだった。もちろん湯上りの生ビールの美味しかったこと筆舌尽くし難し。(本文参照)
(コースタイム)
JR福工大前駅10:32⇒(バス)⇒立花小学校前10:47 48→(修験者の滝経由)→クスノキ原生林11:22 32→屏風岩11:35 37→立花山11:46 12:17→下原分岐12:30→三日月山12:45 13:00→下原2丁目(下山口)13:23→香椎への本道13:35 39⇒(タクシー)⇒千早・極楽湯14:00
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
10月4日(土) 足立山森林公園ランのつもりが小文字山〜足立山トレッキング
まだまだ日差しは強いが、10月ともなれば爽やかな風が秋本番を思い起こさせるに十分だ。そこで緑陰のランエクササイズを思いつき、小倉北区の足立山森林公園へと取った。車なら手向(たむけ)山の峠を越し、都市高速・富野 I.C交差点を左折すればほどなくの距離。多少のアップダウンを我慢すれば緑陰は保障付なのだ。先ずはランスタート地点と定めた公園の北端、メモリアルクロスまで乗り付け、南端の安部山公園目指して、ゆるゆるとウォームアップランのつもりだったが、木々の間から垣間見る青空を認めると、山のてっぺんからの眺望が気になった。ちょうどここは小文字山(標高366m)の登山口でもあり、ものの20分もあれば小倉市街と関門海峡方面の眺望随一の頂に立てる筈。ならば緑陰ランはひとまずお預けとして小文字山登山も悪くはなかろう、と思い立ったが、眺望に魅せられて、そのまま足立山までトレッキング。下りは妙見神社へ降りて遊歩道をメモリアルクロスまで駆けた。(本文参照)
(コースタイム)
足立山森林公園メモリアルクロス(小文字山登山口)13:15→小文字山13:40 53→足立山14:38 52 →妙見上宮分岐14:58 15:00→妙見神社(足立山登山口)15:42→メモリアルクロス15:55
(参加者) 栗秋
10月12日(日) 宗像四塚連峰縦走第一弾! 城山〜金山 極上の照葉樹林を歩く
毎日博多への通勤途上、車窓から見つづけてきた山、城山(じょうやま369m)にカミさんと登った。宗像市と遠賀郡岡垣町の境にどっしりと構えるこの山は、JR教育大前駅から40〜50分、マイカーなら中腹の登山口から30分ほどで登れる手軽な山なので、多くのハイカーで賑わっている。その証拠に道すがら大勢の家族連れや中高年グループと逢い、または前後して登り、人気の高さを実感するとともに、念願の山頂を踏んでようやくの感ひとしおと言ったところ。もちろんこの山だけではもったいないので、北へ連なる金山(317m)を踏み、地蔵峠に降り立って、帰路はJR赤間駅まで舗装路のテクテクハイクを敢行。(本文参照)
(コースタイム)
JR教育大前駅10:17→城山水(登山口)10:33 36→城山11:09 27 →石峠11:58 12:00→金山・南岳12:19 24→金山・北岳12:36 55→地蔵峠13:30 35→JR赤間駅14:42 歩行距離約11k
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
10月12日(日)日本山岳会行事の一環で上野峡〜福智山〜牛斬山〜採銅所を歩く
10月11日 北九州にて(社)日本山岳会の第24回全国支部懇談会が行われこれに参加。ホテル「二ユータガワ」にて15.00より懇談会 記念講演「松本清張と小倉」を聞き18.00より懇親会。本部からの宮下会長以下参加の約200名の先輩や友人知人達との交友をふかめた。翌12日 記念登山はAコースの福智山を選びこれに85名の全国からの岳友達と登った。上野峡ー白糸の滝ー山頂約2時間で登りここから団体行動をはなれて下川君と2人で九州自然歩道を約4時間かけて福智山ー赤牟田ノ辻ー焼立山ー牛斬山ー採銅所駅まで縦走し事前に連絡していた従兄弟の香春町在住のN君と合流。上野峡まで車を回収してもらい帰路についた。好天にめぐまれて前半は交流登山、後半は福智山系の気持ちよい山歩きを2人で楽しんだ一日だった。
(参加者) 加藤、その他大勢。縦走は加藤、下川(ひこさんクラブ)
10月18日(土) 宗像四塚連峰縦走第二弾!孔大寺山〜湯川山を歩き完全踏破!
先週、宗像四塚(よつづか)連峰の南半分、城山〜金山を縦走して地蔵峠に降り立った。ならば性分として残りの宿題を片付けねばどうも落ち着かぬ。つまりは地蔵峠〜孔大寺(こだいし)山〜垂見峠〜湯川山〜承福寺と歩き、宗像四塚連峰完全踏破を達成せねばとの思いである。おっとしかしたかだか縦走距離で16kほど、標高400〜500mの準里山を2回に分けての行程だもの。「完全踏破達成!」などと大仰な表現は慎みたいが、今まで殆ど登ることのなかったカミさん同伴という意味で、ちょっぴり大仰な表現となったか。(本文参照)
(コースタイム)
JR赤間駅9:20⇒(タクシー)⇒地蔵峠9:31 33→山田地蔵尊への分岐10:12→孔大寺神社への分岐10:21→孔大寺山10:23 28→松尾のピーク10:59 11:05→垂見峠11:25 28→内浦分岐11:42→NTT無線中継塔12:00 02→九電中継塔12:16→湯川山12:24 13:10→承福寺13:48 57→高向バス停14:23 27⇒(西鉄バス)⇒JR赤間駅14:54 歩行距離約12k
(参加者) 栗秋、悦子(妻)
11月8〜9日(土〜日) 晩秋の霧島には霧雨、湯煙、ほろ酔いがお似合いの巻
会社の山仲間と2年越しの懸案であった霧島山行がようやく実現の運びとなった。目的はズバリ、韓国岳〜獅子戸岳〜新燃岳〜高千穂峰の縦走。個人的には過去3回(83、84、89年)チャンスをうかがったが、いずれも天候不良で韓国岳、高千穂峰それぞれのピークハントで終わっており、完全縦走の宿題を20年近く抱えたまま今に至っている。ゆえに勢いボルテージは上がったまま霧島入りとなったが、問題はまたしても不機嫌な空模様にあった。それでも人吉付近では雲間から薄日も差し込んできて、少しばかりの期待を抱いたが、えびのI.Cから仰ぎ見る霧島山群は全くの雲の中。それを裏付けるように中腹の白鳥温泉以降は、霧の中を彷徨するように上り詰め、ますます濃くなった霧に戸惑いつつも霧島高原を横断して、今回の世話役・M島氏の待つ高千穂河原へと辿り着いたのだ。とまぁここまではスケジュールどおりだったか。
しかし相も変わらず濃い霧と小雨の織り成す寒々としたシチュエーションでは、下界で見せた盛り上がりは失せ、士気は萎むいっぽうであって、リーダー・M島氏の強い促しがなければ、ビジターセンターを冷やかすぐらいで早々と近在の温泉巡りへと繰り出していたに違いないのだ。その意味で易きに流れつつあった我々、日和見トリオの範を正し、計画どおり高千穂峰へと導いてくれた彼の功績は限りなく大きい、と言ってしまおう。ねぇ、ツルタさん!
さてシリアスモードへの切替えに多少の時間は要したものの、登ると決まれば「霧島ならこそ霧雨が似合うのさ!」とヤセ我慢を発露しつつの出発だ。先ずは鳥居をくぐって白砂利道から古宮址の天孫降臨祭斎場の右手を抜け、よく整備された石畳を登る。紅葉の盛りは過ぎて久しいが、周りはアカマツ林の中、アオハダ、リョウブ、ヤシャブシなど落葉樹は葉を落とし、雨に濡れたヤマボウシの赤い実は、しどけなく妖艶て悩ましい。やがて木立は低くなり、それも過ぎると赤茶けた火山礫の急坂に差し掛かり、霧に隠れたガレ場をただただ登ることだけに専念するといったあんばいである。
そして火口の縁(と思われる)に達すると、ゆるやかな登りから平坦へと変わり、同時に赤茶けた岩塊から黒く細かな砂礫へと移り変わるさまが、ミルク色に包まれた白い世界の真っ只中で、はっきり視覚に残りうる光景でもあった。まさに「馬ノ背」から御鉢東端の鞍部へと進んでいる実感が涌いてくるひとときであったが、五里霧中の歩きゆえに想像力がかき立てられ、逆に印象に残る登路だったと申し述べたい(負け惜しみかぃ?)。
さてそこからは砂混じりの滑りやすいガレ場が山頂までつづき最後の難関である。足の運びと力の入れようによっては一歩前進、半歩後退を余儀なくされるので、ここは一気呵成に登ることが肝要である。そしてほどなく風と霧雨の鈍頂へ辿り着いたが、ガスの中から天の逆鉾と高千穂峰の標柱を確認して、ようやく頂を実感したのだった。あぁ20年前の山頂もまったくの霧の中だったし、今回もまた360度の大パノラマは想像するしかなかったが、晴れ渡った三度目の登頂はいったい何時になることかしらん。宿題がより鮮明になったことだけは確かであって、先ずはこのウップンを湯煙(えびの高原温泉)で洗い流し、夕宴会にぶつけざるを得なかったという短絡的事情はゆるぎなかったが、おっとこれは言わずもがなですね。
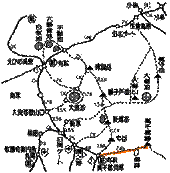


霧島概念図 ガスに煙る高千穂峰の頂 池めぐりコースの中間点、白紫池畔にて
翌9日、天気予報はまったく当たる。しとしとと雨は降り続き、周りは乳白色の世界。雨も上がり視界もそこそこなら、韓国岳から新燃岳を踏み高千穂河原までの縦走も余裕をもって果たせる位置と時刻なのに、と悔やむことしきり。おっともしたらの話はやめよう。ここは潔くえびの高原池めぐりコースへと繰り出し、雨に煙る森と池の風情を愉しむことにしようぞ。
(コースタイム)11/8 JR門司駅7:01⇒(リレーつばめ3号〜快速)⇒JR南福岡駅8:18 25⇒(車)⇒高千穂河原12:14 30→高千穂峰13:50 14:22→高千穂河原15:17 45⇒(車)⇒えびの高原温泉ホテル16:00
11/9 えびの高原池めぐり(宿8:00→白紫池→白鳥山北展望台→六観音御池→不動池→宿9:42) えびの高原温泉ホテル10:55⇒(車)⇒JR南福岡駅14:07 13⇒(快速)⇒JR門司駅16:40
(参加者) 栗秋、他3名
11月15日(土) 紅葉を求めて 晩秋の英彦山を歩く
さいたま在住の岳友・H島君のリクエストで英彦山に登ろうということになった。小倉での出張の帰り、週末に英彦山に登り紅葉を愛でようとの目論見だが、もちろん異論などあろう筈はなく、ホスト役としては精一杯、郷土の山を案内してそのよさを喧伝せねばとの思いも重なった。
で空模様は午前中は晴れ、午後雲が広がり夕刻から雨と何とか滑り込みセーフの予報にひとまず安堵感に浸った。と言うのも先週の霧島登山は雨で目的が果たせなかったので、今度こそはすっきりした山歩きがしたかったし、鮮やかな紅葉は青空の下で映えるからである。その意味でこの風情を愉しむのは午前中が勝負と心得た。
さて登路は奉幣殿から正面ルートを中岳へ、下りは南岳経由で鬼杉から玉屋神社を経由して奉幣殿へ戻るコースを取ったが、この時期の週末だもの、別所駐車場や奉幣殿界隈の混雑ぶりは予想の範疇をかるく超えていささか閉口気味だったことも記しておきたい。まぁそれでも登路のそちこちでは鮮やかな彩りの紅葉に触れ、フィトンチッドいっぱい、鬱蒼とした森の精にもこころ洗われて和んだワンディハイクだったが、山頂からの眺望も晴れ渡った蒼空と相まって申し分なし。しかし空模様は南岳からの下りで早くも曇天と化し、急激な変わりようには少なからず戸惑いを隠せなかったのだ。それでも下山後、英彦山温泉・しゃくなげ荘に着いたころから本格的に降り始めたので、滑り込みセーフに相違なかったが、いささか予報のスピートを超えていて、慌しさの残る山行だったことも否めなかったね。



中岳山頂でのひととき 鬼杉コースの途中 玉屋神社から臨む谷間の紅葉
(コースタイム)
門司7:40⇒(車)⇒神宮下駐車場9:10 22→奉幣殿9:29 30→一ノ岳展望所9:47 50→中岳10:30 40→南岳10:46 59→鬼杉11:38 43→玉屋神社12:15(昼食)36→奉幣殿13:11 13→神宮下駐車場13:17 30⇒(車)⇒英彦山温泉・しゃくなげ荘入湯 13:40 14:40⇒(車・新北九州空港経由)⇒門司17:50 歩行距離約7k
(参加者)栗秋、他1名
11月21〜23日(金〜日) おじさん二人、晩秋・快晴の釜山アルプス・金井山を歩く
9月中旬、カミさんと釜山アルプスは金井山(クムジョンサン)の縦走は行程上 南門から東門を経てこの山塊の最高峰・姑堂峰(コダンボン802m)を仰ぎ見る展望ポイントまで辿り着くのがやっとで、全山縦走は時間切れで断念と相成った。となるとこの宿題は早い時期に果たさなければどうも落ち着かない。そこで挟間兄を誘い、霜月の下旬に決行。もちろん下山後は東莱(ドンネ)温泉・虚心庁(ホシンチョン)へ直行して、おゆぴにすととしての大儀も立てた。
(本文参照)
(コースタイム)
11月22日 金井山全山縦走
南浦洞(宿)7:05→南浦洞駅7:10 23⇒(地下鉄)⇒梵魚寺(ポモサ)駅8:06→バスターミナル8:10 16⇒(タクシー)⇒梵魚寺8:22→登山口8:37→北門9:10 20→姑堂峰(コダンボン・801m)9:38 48→北門10:07 09→第4望楼10:22 28→第3望楼10:36 43→展望ポイント(前回到達点)10:55 11:08→東門11:28 30→山城峠11:37 40→南門12:02 06→第1望楼12:20→玻璃峰(パリボン・615m)12:42 56→上鶏峰(サンゲボン・645m)13:20 25→稜線上のピーク(ヘリポートらしき台地)13:42 53→南門14:07 08→ケーブル山上駅前14:27 28→金剛(クムガン)公園下15:07 16⇒(タクシー)⇒温泉場(オンチョンジャン)の虚心庁(ホシンチョン)入湯15:25 16:35→温泉場駅16:42 45⇒(地下鉄)⇒南浦洞駅17:17→宿17:25
(参加者)挾間、栗秋