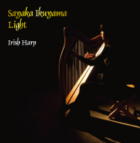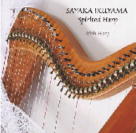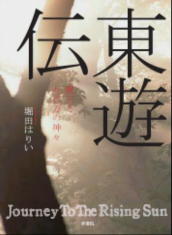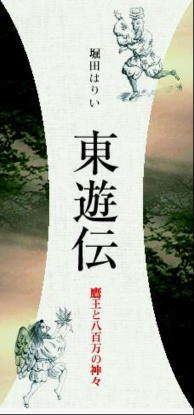『東遊伝』あらすじ
天神の子として生まれたアルタン(黄金の意)はモンゴル相撲の国内大会のジュニアの部で優勝。その後、ヒノモトの国の大相撲の力士となる。四股名は那瑠(ナル=太陽)とした。土俵に上がるや快進撃をする。が、幕内に上がるや、行き詰まり、帰国も考えていた、そんなある時、福岡の大鷹神社という別名「相撲神社」から神相撲の力士として招かれる。それが那瑠の運命を大きく変えることになる。
福岡空港に到着する前から那瑠は古代帆船の幻影を見たり、空港で立ち寄った梅ヶ枝餅屋で、王宮の幻影を見たり、不思議な体験をする。それが那瑠の前世と関わりがあるとは、つゆ知らず・・・
不思議なことに、モンゴルの家に古来より伝わる黄金の鷹の像とケルト文様の黄金の指輪が、大鷹神社にも伝わっていたのだった・・・。
「Light」を聴けば、アイリッシュ・ミュージックとスコティッシュ・ミュージックの技と型に精通した音楽家であることがはっきりとわかる。魅惑の精妙さと、演奏法の、いくつかの歓喜の展開が彼女の演奏に宿っていて、壮麗な気分を経験させる。(イギリスの音楽雑誌「fROOTS」の2012年6月号)
「ハープだけの完全ソロでケルト系伝承曲などを計13曲。過去聴いたハープのソロ作品では最高の一枚。素晴らしい音楽家だ」(松山晋也 ミュージック・マガジン 2012年1月号より)
「瑞々しい感性がハープの一音一音に精霊のごとく宿っており、ハープだけの完全ソロ・アルバムながら、マジカルな響きに満ちている」(遠藤哲夫 ストレンジ・デイズ 2012年3月号より)
|
|
祭りの福岡から古代にタイムスリップ
『東遊伝〜鷹王と八百万の神々〜』(梓書院刊) (Journey To The Rising Sun) 著者:堀田はりい 挿絵:生山早弥香 扉絵:梅田千鶴 好評発売中!
 |
 |
限りな壮大な、古代歴史ファンタジー巨篇
ケルト、モンゴル、韓国、日本の神話、伝説、歴史、民俗学
などをもとに、古代人の感性と目線に立って創作した「ハリー・
ポッター」的に、或いは、「西遊記」以上に壮大な、日本人の
遠い以上記憶を呼び覚ます不思議物語。そのスケールは、愉
快な神々をも巻き込み、時空を超え、汎ユーラシア。
|
この物語は、古代ケルト、古代モンゴル、古代朝鮮、そして倭国(筑紫、豊国、古大宰
府、壱岐)に生きた鍛冶神の鷹を奉じた人々と、その人々と縁のあった人々が、千数
百年の時を経て、21世紀のヒノモトの国で、様々な、新たなつながり方で再会する、
時空を超えた「旅」と「祭」と「和」の物語である。また、八百万の神々の国に行った青
い目のモンゴル人力士鷹王が、ヒノモトの国の相撲道を極め、相撲界の王座に着く途
方もない偉人伝でもある。(「東遊伝」巻頭言より) |
|
ケルトからモンゴル、三国時代の韓半島、そして筑紫国へと、遙かなる草原の道
を辿る精神の旅。ケルトの竪琴から巫楽に龍神を招来する歌舞音曲。"金"とい
う永遠の命が繋ぐ神々との交流。力士の持つ邪破の力を縦糸に、ニール・ヤン
グやジョン・レノンまで現れる言霊の世界。世界の音楽好きには堪られないこれ
ぞ東遊伝。星川京児(音楽プロデューサー。NHK「にっぽん、心の仏像」他)
堀田はりいと同じくぼくは九州にいる。外国の大衆音楽に不思議な親近感を覚え
ることがある。スポーツのかなたに古代祭祀を見ることがある。九州人を熱くさせ
るものは忘却のかなたから来るという直感。はりいさんがこう書きたくなる気持ち
がぼくにはよくわかる。長谷川集平(絵本作家・ミュージシャン)
現代と古代、現世と神々の世界の垣根を軽く乗り越えたお話、楽しかったです。
読んでいて一番心地よかったのは、舞楽や相撲が神々に捧げられて、無我の境
地になって執り行われる場面の数々です。芸術と武芸が現世の人間の為だけの
ものではなく、本来は、目に見えない天地精霊や祖霊、神々に捧げられる祭祀だ
ったという事に感銘を受けました。大切なことを教えていただいたと感謝いたして
おります。松本峭山 (尺八奏者)
|
|
●主人公アルタン(四股名那瑠{ナル}。後の鷹王。モンゴル人力士)の前世(アル
タン。後の鷹王。高句麗人力士で杖鼓奏者)の家族と恋人:ニーア(母。ケルト人。
神官。竪琴奏者)、ハルチャ(父。蒙古人。力士)、カノン(双子の妹。巫女。竪琴
奏者)、ハナ(恋人。高句麗人。巫女、琴奏者) |
●その他の登場人物:薩夜麻(筑紫国君主)、菅原道真(天神さま)、ゴバノン(ケル
トの村の神官)、宗像三女神、朱蒙、宝蔵王、泉蓋蘇文(淵蓋蘇文)、鬼室福信、
翹岐、蘇我入鹿、高句麗の竜神、カスヤの竜神、孫(壱岐の金物屋の主人)、獅子
王(豊前国力士)、アリオン(突厥国天地神堂大神官)、ミユ(高句麗国天地神堂大
神官)、裟婆(豊前国君主)、ヌカタ(百済の宮廷歌人)、チャンスン(高句麗国境の
守り神)、ニイル(吟遊歌人)、むのたもん(「あれこれ特ダネ」の司会者)、アメノウ
ズメノミコト他多数。 |
●時代は七世紀半ば。古代ケルトから古代モンゴル、古代朝鮮、そして倭国へと日の
出づる方角へと旅する時空を超えた古代歴史ファンタジー。 |
●現世、前世、八百万の神々の国の三つの世界が魔法的に絡み合って、物語は進
む。 |
●物語の中に物語がある。 物語は「音」感覚に富み、四次元的かつ映像的で、一部
語り部的。 |
●ケルト音楽、フォーク、ロック、モンゴル音楽、仮面劇、伎楽、農楽、韓国舞踊、雅
楽、童謡、和歌、万葉歌、神歌、神楽、物語歌、英雄叙事詩、鎮魂歌、沖縄民謡、博
多どんたく、博多にわか、酒造り歌、相撲甚句、迎月歌、婚礼歌、そしてラップ音楽な
ど色々な音楽や芸能が登場する。 |
●重要無形文化財の「傀儡子の舞と神相撲」の祖型を推究し、ファンタジー化して再
現。 |
●主人公の前世の母親は、ケルトの村のドルイドの娘で竪琴の奏者。あるとき、人生
を激変させる事件が・・・。 |
●渡来人が多く暮らす大野城と「大宰府」以前の、国際都市で水の都の「太宰府」が渡
来人の歌人や楽師や巫女の目線で鮮やかに蘇る。 |
| ●「スカボロフェア」が本来の妖精と人間との問答歌として、古代ケルトの村に蘇る。 |
| ●カナダのロック・シンガー、ニール・ヤングの前世が放浪の吟遊歌人で登場する。 |
●日本の神話の神々のほか、徳光(トクノヒカル:雷神の子)、田之守留(タノマモル。
田の神さま。通称タモル)、小泉(オノイズミ:泉の神さま)、オンクロウなどユニークな
神々がいっぱい登場する。 |
| ●七世紀半ばの東アジアの激動の歴史を垣間見ることができる。 |
●相撲を見る目がアジア的スケールで、広く深く養われる。神話時代からの相撲の精
神が楽しく学べる。 |
●付録の登場人物の系図と、登場する生き物(人間、猫)の前世と現世の関係表は発
見多数?で、見てのお楽しみ。 |
表紙をめくったときから、遥かなる『物語り』の旅人。 |
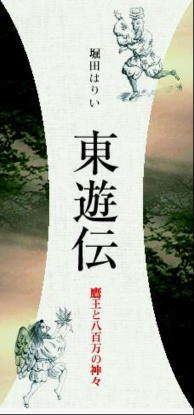
「東遊伝」に関連した話題を、広く綴っています。
当サイトはリンク・フリーです。よろしければ、下のバナーをお使い下さい。
書評
日本発、いや東アジア発の本格的ファンタジー小説だと思いました。
現代の現世、神々の国、そして古代の前世の三つの世界を行き来すること自体、スケールが大きいのですが、それに加えて、誘拐にあったり、国と国の交流等で、古代ケルトの村から古代モンゴル、高句麗、倭国へと地球規模で旅するという物語の距離的スケールも大きく、毎日、旅する気分(時空も)で読み進みました。
続きを読む
(amazonカスタマー・レビュー)
音楽雑誌「包(パオ)」の初代編集長たる堀田はりいの小説は、副題「鷹王と八百万の神々」のごとく、芸術に対する芸能のありよう、その何とも生き生きと騒がしいさまが際立つ。ごくごく単純化するなら、モンゴルの青年がやってきて力士として活躍、そしてその経緯のなかで遭遇する過去と現在の神話・幻想の世界、ということになるだろうが、そこでは音・音楽の世界が全篇に満ちている。
(『intoxicate』2012年2月号。小沼純一:音楽・文芸批評家/早稲田大学教授)
インタビュー
ええ、ハープも出てきますよ。物語の主人公の母親と妹がハープ奏者なものですから、ちょくちょくハープを演奏する場面があります。
で、ぼくの本、東遊伝ですけど、ひがしに、あそぶに、伝説の伝で、東遊伝というタイトルなんですが、主人公がモンゴル人の力士で、その力士がある事件で神々の国に行くんですね。そこで、ある神さまに「前世が古代の日本、つまり倭国で活躍した渡来人力士で、韓国の太鼓の演奏家だったことを教えられるんです。そこから前世の親の世代からの物語が始まるんです。
物語はですね。ヨーロッパの東はしのケルト人の村から始まって、古代のモンゴル、古代の韓国、そして古代の福岡、そして古代の大分。東から西へと旅する西遊記とは逆コースで、二世代に渡って日の出の方角に旅して、東の終着点が倭国という設定なんです。
大分の関連ですと、主人公が力士なものですから、双葉山が理想としたという木鶏の夢を主人公が見る場面があったり、中津の傀儡相撲の祭りや日田の鬼伝説なんかも、物語の中で夢物語のように描いているんです。
とにかく、大長編の、凄く壮大な物語なんです。
(OBSラジオのインタビューより抜粋)
「東遊伝」正誤表
●P136の上段12行目:ニーアもハナは⇒(正)
ニーアもハナも
●P189の上段6行目:芸術品ですありますね。⇒(正)
芸術品でありますね。
●P299の下段1行目:あけなく⇒(正)
あっけなく
P315の下段最後から3行目:●「白い」の後に入るべき「真珠」という文字が脱字。
●P318の下段最後から3行目
マサヨシ⇒(正)アサヨシ