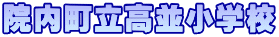
院内町にあった小学校です。院内町から?ダム方向に入っていったところにありました。今は、体育館とプールが残っています。結構新しい感じです。それもそのはず中学校の廃校後に作ったそうです。ここは元々高並中学校があったそうです。中学校の廃校後小学校が入ったそうです。ここの卒業生は、両川小学校の児童と高両中学校(すでに廃校)に進学しました。最初の文字の高と両を使っています。昭和62年に両川小学校と統合し院内北部小学校になりました。小学校は、丘の上に一棟残っています。ただ、立ち入り禁止になっています。
 作詞 作曲 不明
作詞 作曲 不明
1 緑の山にかこまれた 高い台地にわが校舎
平和の光に包まれて みんなにこにこよい子たち
希望抱いて進んでいく
2 瞳かがやきむつみあい 自治の集いにみがかれて
正しく雄々しく手を組んで 僕等わたしらよい子たち
はげましながら進んでいく
3 どっしり聳える鹿嵐に 薫るきれいな石楠花
静かな村に咲きつどう 伸びる若芽のよい子たち

考える子 明るい子 たくましい子
 |
この体育館は、後で建ったようです。 |
 |
プールも後のようです。 |
 |
閉校記念碑です。 |
 |
100周年記念碑です。 |
 |
更衣室もしっかり残っています。 |
 |
ここに来るまでは、少し上のところに小学校はあったそうです。 |

明治 5年 4月 1日 寺小屋を小野武彦宅に統合して舟木校の教務開始
明治 8年 4月 校舎改築(間口11,5間 奥行き3間)
明治20年 学校令改定により艦材尋常小学校(下船村)と改称し小野川内村に小野川尋常小学校を設立
明治26年 6月 大暴風雨により校舎転覆、百社宮招元思所及び下舟木佐藤廣市宅で授業
明治27年 3月 校舎を前の跡地に建設(13間×3.5間1棟・3間×2.5間1棟)
明治32年 1月 四ヶ村組合立院内高等小学校の分教場を茶屋の原に設置
高等小学校1,2年生まで通学 3年生は茶屋の原。
明治34年 4月 校舎増築
明治35年 4月 裁縫科を設置
明治36年 3月 四ヶ村組合立院内高等小学校解散により分教場廃止 高等科を
設置し尋常高等小学校になる
明治41年 4月 1日 学制改革により尋常科6年制義務教育 高等科は2年制
明治41年 9月10日 校旗制定 開校記念日と定める
明治43年 3月 校舎増築落成式
大正 3年 4月 農業補習学校を付設する
11月26日 高並橋完成。落成式に参加
大正 7年10月 尋常科5年生以上が、合同修学旅行(別府、大分、佐賀関)
大正11年11月 9日 陸軍特別大演習拝観のため尋常小学校5年生以上豊川小学校に宿泊
大正13年 5月20日 一学級増設し三四年生を分離する
大正14年 9月16日 宇佐郡連合体育会に参加(宇佐神宮)
昭和 5年12月14日 小稲に木造二階建て校舎新築落成移転 小川内川分教場廃止
昭和 8年 1月23日 郷土軍戦勝祈願祭尋常5年生以上参拝
昭和14年 7月14日 応召家庭の労働奉仕を三日間行う
昭和15年 3月18日 期限2600年記念植樹を大重見に四町歩行う
昭和16年 4月 1日 国民学校令により高並国民学校と改称する
昭和17年 3月26日 体位優良校として表彰される
昭和22年 4月 1日 学校教育法公布により高並小学校となり高等科を廃止する
昭和24年 7月14日 JRC結成
昭和27年11月 1日 大分県学校新聞コンクール二位
昭和28年12月16日 子ども銀行全国優良校賞
昭和31年 1月 1日 五ヶ村合併 院内村立高並小学校となる
昭和31年 7月14日 南校舎竣工(教室2棟倉庫10坪)
8月13日 水道工事完成(天水引水)
昭和33年 4月 8日 テレビ施設初完成
昭和34年 1月16日 校旗制定
昭和35年10月 町制施行 院内町立高並小学校
昭和37年 5月 4日 新校舎落成 運動場拡張
昭和38年 8月 6日 鼓笛隊編成
昭和38年10月11日 ミルク給食調理室完成
昭和42年11月25日 校庭安全柵設置
昭和47年12月15日 創立100周年記念式 記念授業(相撲場、岩石園)
昭和56年 4月12日 保健室完成
閉校誌
明治 5年 4月 1日 寺子屋を統合して学制制度公布前に舟木小学校を創立する 校舎は民家を充当しており中央の行政方針を速やかに察知した先覚者がいたのであろう
8月 3日 学制制度発布さる(下等小学校4年・上等小学校4年)
明治 8年 4月 舟木小学校新築 位置は下舟木村百社宮のしもの方(間口十一,五間、奥行き三間)
明治11年 4月 小学校教育規則が改正され小学校を大別して上・下二棟とし、さらに小分けして各八級に分け半年ごとに試験をして進級させる制度を取る
明治14年11月 県令より小学校設置区と校数が規定される(当時宇佐郡の学校は三六校である 現在の院内町では明治五年舟木小学校 明治七年香下小学校 明治八年斉藤小学校 定別当小学校 恵良小学校の五校であった)
明治15年 6月 小学校規則改正初等・中等を各三ヶ年高等を二ヶ年とし通じて八ヶ年とした 進級試験の実施 郡役所学事担当が各学校を巡回し進級試験を実施した 試験の結果特に優秀のものには大分県の名において賞状を授与した 小稲村の生徒の賞状は現在残されたものの中の数少ない一葉である
明治19年 4月 小学校令制定 文部大臣森有礼は、国民皆学・国運の進展を目指し制度を更に改革し小学校令を施行した。尋常・高等の二種に分け修業年限を各四ヶ年とし尋常小学校を義務教育とした。しかし別に尋常小学校に代わるものとして三ヶ年の簡易小学校を設けた。簡易科は、授業料も免除され修業年限も免除され修業年限も三年なので女子の多くが希望していた(明治23年廃止)
明治20年 学校令改正 舟木小学校を艦材尋常小学校(下舟木)と改称した。この名称の由来は、神功皇后が三韓征伐のときに上舟木の地より御船の材を取らした故事に因む。小野川内村に小野川内尋常小学校を設立
明治23年 4月 地方学事通則・設備準則が発令され高等小学校は二年・三年又は四年とし経費は市町村から支出することとなる(宇佐郡下では本校三十六校・分校二十一校あり)
10月 「協育に関する勅語」発布
明治24年 4月 学校令改制により既に設立されていた小野川内村の簡易学校簡易科を廃し艦材尋常小学校の小野川内分教場となる
明治26年 6月 大暴風雨により校舎が転覆し百社宮招魂所及び下舟木民家で授業を行う。
明治27年 3月10日 校舎を前の跡地に建設(13間に3・5間一棟と三間に二・五間一棟)
8月 日清戦争起こる
明治30年 4月 四ヶ村組合立院内高等小学校(南院内村・東院内村・院内村・高並村)を東院内村山城の茶屋の原に設置
明治32年 1月 宇佐郡高等小学校組合を解散。院内高等小学校を設置したが,本村より通学する生徒遠路困難のため艦材小学校に院内高等小学校分教場を設置し高等科二年生までが通学した。三年生は茶屋の原に通った。
明治33年10月 小学校令の改正により尋常小学校に高等科二年制の付設が認められた。
明治34年 4月 校舎を増築(長さ五間半・横三軒半経費弐百参拾円也)校訓制定一,忠君愛国を旨トスベシ 一、神佛ヲ尊敬スベシ 一、父母ニ孝養ナルベシ 一、兄弟姉妹ヨクスルベシ 一、長ヲ敬ヒ幼ヲ扶クベシ 一、朋友ニ親切ナルベシ 一、行儀ヲ能クスベシ 一、身体ノ健全ヲ保ツベシ 一、恩ヲ忘ルベカラズ 一、妄リニ欠席スベカラズ 一、父母ノ業務ヲ助クベシ 一、自治ノ心ヲ養フベシ 一、忍耐ナルベシ 一、過ヲ改ムベシ 一、勤勉節倹ナルベシ 一、有價樹木ヲ増養スベシ
明治35年 4月 裁縫科を設置
明治36年 3月 小学校令施工規則改正。四ヶ村組合立高等小学校解散により同校分教場を廃止
4月 教科書が国定となる
6月 高等科を新設し艦材尋常高等小学校となる
明治37年 2月 日露戦争起こる
明治40年 1月10日 高等科児童職員、別府・大分へ(皇太子殿下本県に行啓、本校児童の手芸作品を天覧、お持ち帰りになられる。)
明治41年 4月 1日 小学校令改正により尋常小学校6年義務制となり高等小学校2年~3年制となる。教科は、日本歴史・地理・理科・図画・唱歌と女子の裁縫が必修となる。 9月10日 校旗を制定し開校記念日を定める
10月13日 戊申詔書発布
明治43年 3月 大分県訓令が出され県費の補助もあり実業補習学校が正規に設置の方向に進んだ。
3月25日 校舎増築完成(総工費産貳荃阡四百参拾壱円九拾壱銭五厘)
大正 3年 4月 1日 農業補修学校併置
第一次世界大戦始まる
10月 第四部連合大運動会(東院内小学校)出場
大正 4年 農業補修科各部落に設立
11月 宇佐神宮境内に於いて郡内小学校児童御大典記念大運動会挙行さる
大正 7年10月 5年以上修学旅行(別府・大分・佐賀関)
大正 8年 地理・歴史・理科の時間増加
11月 第四部連合学芸会に出席(5年以上)
大正11年 2月 6日 高並橋が落成し式に参列(眼鏡橋)
11月 9日 陸軍特別大演習拝観のため豊川小学校に宿泊す(5年以上)
12月 蔬菜品評会
大正12年 3月10日 中津連隊より大尉来校軍事講話
4月 身体検査を行う
6月 農繁休業を行う(7日間)
大正13年 5月20日 1学級増設し3・4年生を分離
大正14年 8月 夏休み宿題として一蛾飼育(児童90名参加)
9月16日 宇佐郡連合体育大会(於宇佐神宮)参加
大正15年 5月 6日 高並村青年訓練所開設
12月 9日 お伽話大会(話し方)
昭和 3年10月10日 県下小学校御真影奉載が始まる(奉安殿の建設計画おこる)
11月 7日 宇佐郡南部庭球大会で優勝
昭和 5年 3月19日 新校舎建築中、土砂崩れのため死亡者でる
11月 長洲女学校、騰宮学館庭球大会で優勝
12月14日 小稲に木造二階建て校舎が新築落成し移転、小野川内分教場を廃止す(敷地は寄付)
昭和 6年 3月 5日 奉安殿の落成式
大貞、長洲女、宇佐中、騰宮学館各庭球大会で優勝
昭和 8年 1月 郷土軍戦勝祈願祭に5年以上参拝(宇佐神宮)
昭和10年 4月 2日 青年学校令公布 これまで実業補習学校と青年訓練所が小学校に併置されていたが一本化され青年学校が誕生した。校長は小学校校長が兼任した
昭和12年 6月 女児生徒千人針を戦地に送る
7月 7日 日華事変起こる
昭和14年 戦地の兵士に対し慰問文発送(二ヶ月に一回)
7月 応召家庭に労働奉仕を三日間行う
昭和15年 2月15日 紀元二六○○年記念旗行列を行う
3月18日 紀元二六○○年記念植樹を大重見に四町歩行う
昭和16年 4月 1日 学校令改正により高並村国民学校と改称さる(初等科六年、高等科二年の計八年間の義務教育となる)
昭和17年 3月 体位優良校として表彰される
昭和19年 1月10日 国民学校教育の戦時非常措置通達
6月 児童疎開要綱制定
昭和20年 8月15日 太平洋戦争終わる
12月 学校内における御真影、奉安殿,勅語証書、忠魂碑等の除去始まる
昭和22年 3月31日 教育基本法並びに学校教育法が制定された
4月 1日 学校教育法により高並小学校と改称し高等科を廃止(いわゆる六・三・三・四制として施行され義務教育が九ヶ年となった)
昭和23年 9月 国定教科書制定を廃止し教科書検定制度実施
昭和24年 7月 JRCを結成
昭和27年11月 大分県学校新聞コンクールで第2位受賞
昭和28年12月 子供銀行全国優良賞を受ける
昭和30年 1月 1日 五か村合併により院内村立高並小学校と改称
3月 ピアノ開き
昭和31年 7月14日 南校舎が竣工(教室二つ25坪と倉庫一つ10坪)
8月 水道工事完成
9月 文部省学力テスト
昭和33年 学校林造成(32年卒業生の記念林として植栽杉300本桧600本)
4月 8日 テレビ施設初めて完成
昭和34年 1月16日 新校旗を制定(寄贈)
昭和35年10月 町制施行により院内町立高並小学校と改称
昭和37年 5月 4日 新校舎落成し運動場が拡張される
昭和38年 8月 6日 鼓笛隊を編成
10月11日 ミルク給食調理室完成
昭和41年10月 大分国体記念温室落成 登下校路舗装完了
昭和42年11月 校庭安全柵を設置
昭和46年 3月 県連合PTA指定研究会発表会(1年次)実施
昭和47年 2月 県連合PTA指定研究会発表会(2年次)実施
12月15日 創立百周年記念式 記念事業を行う
昭和50年 7月 NHK合唱コンクール出場(大分)
昭和53年11月 ドーム付きすべり台新設
昭和54年 2月 給食コンテナ置き場新設
4月 校庭安全用フェンス改修
昭和55年 2月 講堂の渡り廊下及び裏山擁壁完成
昭和56年 4月12日 保健室完成
昭和57年12月 図書室設置(プレハブ)
昭和59年 5月 印刷室改造
11月 学校林間伐
昭和60年 8月 講堂天井張り替え 講堂・職員室の照明灯増設
11月13日 院内町助成研究発表会(第一年次)
昭和61年 5月 高並小学校閉校実行委員会結成
9月28日 閉校記念秋季大運動会(地区民総参加)
10月 8日 院内町助成研究発表会(第二年次)テーマ(一人ひとりの表現力を伸ばすための指導は、どうあればよいか)
11月 5日 高並・両川閉校記念合同遠足(安心院旅行村)
12月 「高並小学校誌」編集終了
高並中学校 (宇佐郡中学校沿革史)
昭和22年 4月 1日 高並村高並小学校に併設さる 初代校長任命さる
5月 5日 開校式 職員数6名 学級数3 生徒数92名
昭和23年 3月25日 第一回卒業式 卒業生23名
昭和24年 3月 第二回卒業式 卒業生35名
10月 1日 高並中学校校舎新築落成
昭和25年 3月 第三回卒業式 卒業生34名
昭和26年 3月 第四回卒業式 卒業生26名
昭和27年 3月 第五回卒業式 卒業生27名
昭和28年 3月 第六回卒業式 卒業生39名
昭和29年 3月 第七回卒業式 卒業生29名
昭和30年 1月 1日 町村合併により院内村立高並中学校と改称
3月 第八回卒業式 卒業生39名
4月 1日 高両中学校へ統合され高並校舎となる
昭和31年 3月 第九回卒業式 卒業生31名
4月 7日 統合中学校始業式 職員数8名 学級数3 生徒数105名
9月30日 高両中学校校舎移転完了
戻る





