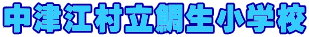
金山で有名な鯛生にあった小学校です。最初は、山の上にありました。その後中学校の閉校後中学校舎に移りました。昔は、何千人もいた地区ですが閉山後は、過疎地になって閉校しました。平成7年町内3小学校の統合で中津江小学校になりました。最初の山の上にあった校舎は、スポーツセンターとして使われていました。ただ、行ったときには取り壊されていました。移転先の小学校は、鯛生中学校でご覧下さい。

作詞 矢野 周蔵 作曲 青本 澄夫
1 津江の山なみ霧はれて みどりの杉の丘の上
明るく元気に伸びてゆく われら鯛生のよい子ども
2 古い歴史はかず多く 川の流れも美しく
強く正しく伸びてゆく われら鯛生のよい子ども
3 酒呑童子のいただきを 朝夕ながめはげみ合い
望みも高く伸びてゆく われら鯛生のよい子ども

はげまし合う子 がんばる子 考える子 はたらく子
 |
テニスコートになっています。左側に校舎がありました。 |
 |
近くの神社から見ました。山の中の学校としては広いかな。 |
 (中津江村史より)
(中津江村史より)
明治11年 1月 鯛生学校創立 字堂山 民家借り入れ
明治19年 小学校義務教育制度 鯛生簡易学校
明治23年10月 教育勅語発布
明治26年 4月 丸蔵小学校分教場となる 四年制 学級数1
明治27年 鯛生金山発見
明治31年 金山開発着手
明治40年 鯛生小学校となる 六年制 学級2
明治40年11月 新校舎完成(田島参一郎の住宅地)530円内500円鉱山寄付
大正 5年 鯛生尋常小学校 八年制 八学級
大正14年 現鯛生小学校整地増築
昭和 2年 教員住宅と学級増で改築
昭和 8年 児童数502名 仮校舎建築
昭和10年 4月 新校舎完成
昭和15年 8月 豪雨で校舎裏崩壊 宿直室全壊
昭和15年 9月 宿直室移転
昭和16年 2月 鯛生国民学校となる
昭和22年 2月 火災全勝 鯛生劇場、排球所で分散教育
昭和22年 4月 鯛生小学校となる
昭和22年 鯛生鉱業所の医療所購入
昭和30年 金山グラウンドに新校舎完成(校舎・講堂・宿直室)
昭和35年 4月 一,二年生が二学級
昭和36年 給食開始 校舎増築
昭和42年 障害児学級開設(7学級)
昭和45年 鯛生金山閉山 児童数132名
昭和46年 鯛生小学校・中学校プール完成
昭和53年 百周年記念
昭和55年 新校舎建築 旧鯛生中学校跡地
昭和56年 新築移転
閉校誌(百周年以後)
昭和53年 8月 創立百周年記念式典を挙行する
昭和55年 9月 新校舎建築に着手する
昭和56年 4月 新校舎にて始業式・授業を開始する 新校舎落成記念式典を挙行する
12月 体育館外部改修工事
昭和58年10月 学校田を設置し初の収穫を祝う
12月 日田郡地教委連絡協議会指定研究発表(少人数・複式について発表する)
昭和60年 3月 日田郡地教委連絡協議会より研究発表の感謝状・記念品を受賞
4月 障害児学級が改称され4学級となる
5月 学校単独給食やめ村小学校共同調理によるセンター給食を開始する 百年基金の残金より剣道防具15組(全校生徒分)を購入して鯛生小学校剣道「鯛生剣山会」が発足
7月 NHK大分放送より「鯛生小学校一輪車乗り」全九州に放映する
昭和61年 9月 校門の門柱を立て替える
昭和62年11月 全九州・大分県へき地教育研究会指定で集合学習仲よし学校を発表(川辺・丸蔵・鯛生による学習)
平成 元年 5月 第26回大分県小学校児童作文コンクール「文集の部」で大分県小国研賞受賞
11月 村勢100周年式典(全校参加)
平成 2年 8月 旧鯛生保育園より遊具施設を小学校に移動
9月 プール建設敷地地鎮祭 プール建設工事着手
平成 3年 1月 プール竣工式典
12月 台風19号により倒壊したフェンスの新設工事に着手
平成 4年 3月 体育館ステージ引き幕完成
平成 5年 3月 運動場南に第2体育倉庫完成
7月 生活用砂場・体育用砂場完成
平成 6年 6月 統合に関する陳情書を村・村議会に提出する 統合に関する案件が6月定例議会に提出され同日可決
9月 閉校事業実行委員会発足(閉校事業に向けて準備始まる)
平成 7月 3月 閉校記念式典を挙行する
戻る

