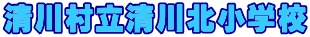
清川村の牧口にあった学校です。平成16年清川村小学校3校の統合により閉校。ただしこの北小学校の校舎を使ったので校舎はそのままです。新制中学ができたときには牧口中学校がここにありました。
大野郡清川村大字砂田1732番地 明治12年創立

作詞 後藤 栄 作曲 田坂 保
1 光は野辺に空青く あおげばはるか四王子に
あした夕べをわく雲の 希望わき立つまなびやは
ちえをみがいて育ちゆく 清川北のわが母校
2 流れは遠く水清く 奥嶽川のわが里の
集いて学ぶ友垣の 力あふるるまなびやは
体きたえて育ちゆく 清川北の我が母校
3 歴史は古く夢若く 名もなつかしい牧口に
あしたとび立つ若鳥の 夢をはぐくむまなびやは
ただひとすじに育ちゆく 清川北の我が母校
校訓は、不明です。
 |
校舎は、鉄筋二階建てです。 |
 |
校舎の端にプールと体育館があります。 |
 |
校舎の横に清川北小学校の閉校記念碑がありました。 |
 |
校門の前に百周年記念碑がありました。 |
 |
令和3年に行きました。清川小学校の校名と校章がありました。 |
 |
運動場も校舎も変わっていませんでした。 |
 |
令和6年に行きました。小学校は、清川小学校に移動し空き校舎になっていました。 |
 |
体育館は、使われているのでしょうか? |
 (清川村史より)
(清川村史より)
明治12年 河宇田学校(天神村小園)牧口学校(砂田村)雨堤学校(雨堤村)日小田学校(三玉村)開校
明治17年 佃学校、河宇田学校と日小田学校を統合、佃学校とする。牧口学校には、砂田村、雨堤村、臼尾村が通う
明治20年 学制改革 佃小学、牧口小学を合併して牧口簡易学校となす。
明治21年 郡内31ケ村組合にて、三重町に大野郡高等小学校が設置され、牧口簡易学校卒業生多数この高等小学校に通う
明治22年 砂田村、雨堤村、臼尾村、三玉村、天神村を合して牧口村となる
明治24年 教育勅語郡役所を経て当小学校に下賜せられる
明治25年 前年発布の小学校令により四月一日学校の位置を牧口村大字砂田二六一番地とし牧口尋常小学校とする 小学校に補習科、唱歌科設置を議決す
天皇陛下正装肖像絹表掛け軸下賜
明治29年 三重町大野郡高等小学校の分校を緒方町に設けることとなり、南緒方村原尻及び牧口村砂谷分校が設置せられた 牧口小学校焼失
明治30年 小学校建築に着手
明治31年 小学校校舎落成
明治32年 三重町大野郡高等小学校牧口分校を廃し郷内八か村の連合を持って第一牧口高等小学校とする
明治33年 小学校に裁縫科を設ける
明治41年 牧口ほか、七か村組合高等小学校を解散し月より牧口小学校に高等科併設する
昭和 4年 校舎増築、二階建て教室四教室を本館裏に増築する
昭和 8年 校舎改築、講堂新築、落成式を行う
昭和16年 牧口国民学校となる
昭和22年 牧口村立牧口小学校となる
昭和30年 町村合併に依り清川村立清川北小学校となる
昭和42年 校旗、校歌制定
昭和48年 鉄筋コンクリート二階建て校舎落成
昭和52年 屋内運動場改築工事起工式 竣工
昭和22年から昭和41年まで清川北中学校併設
閉校誌
慶応 3年 緒方郷は、岡城主中川久成氏の領地に属し8村を成す。
明治 5年 学制発布
明治 6年 各大学区に(大野郡五大区)に学区取り締まりを置く 区内小学校区に学校世話方を任命した。大野郡は15名、後に学務委員となる 最初の4年間を下等小学校
、後の4年間を上等小学校とする
明治12年 河宇田小学校(緒方町天神小園)ができる 砂田雨堤小学校(砂田)ができる 日小田小学校(三玉)ができる
明治17年 佃小学校(河宇田・日小田両校が統合する)ができる 砂田小学校ができる
(砂田・雨堤・臼尾から通学する)
明治19年 小学校令により尋常小学校(4年)、高等小学校(4年)とし尋常小学校を義務制とする 村内伏野・六種にも設置する 小学校簡易科(簡易学校)の設置が認めら
れる。
明治20年 牧口簡易学校設立される(雨堤・佃・牧口学校合併)
明治23年 教室増築する。これは砂田地区の有志の寄付金による。
明治24年 教育勅語の謄本が下賜される
明治26年 牧口尋常小学校が発足する 位置は砂田261番地 補習科・唱歌科を設置する 学校委員を設置する(人気3年)(学級数1)
明治29年 大野郡高等小学校牧口分教場が設置される。位置は、砂田の民家(12月まで)牧口小学校校舎一教室を増築する 牧口小学校消失、職員室を
含め校舎一棟と帳簿、書籍、一切消失。付近の土地を買い入れ、校地を拡張する
明治30年 小学校校舎の建築に取りかかる (学級数2)
明治31年 牧口小学校校舎落成
明治32年 緒方郷8ケ村組合立牧口高等小学校発足。校舎増築 (学級数3)
明治33年 小学校に裁縫科(今の家庭科)できる (学級数4)
明治37年 各区から学校基本財産として山林9反歩の寄付を受ける(学級数5)
明治38年 学校林に松・杉を植林する (学級数6)
明治39年 2教室を増築・運動場を拡張する
明治40年 義務教育が6ケ年になる 牧口尋常小学校の校歌ができる
明治41年 牧口外7ケ村組合立高等小学校を解散する決議が成される
明治42年 緒方郷組合立高等小学校を解散する 財産処分をし牧口尋常小学校の校舎になる 牧口小学校に高等科を併置する(以後終戦まで続く)
大正 4年 大正天皇即位大典 小学校で遙賀式を行う
大正 7年 郡内小学校に先駆け体育器械を完備する
大正 9年 巨費を投じて理科器具を購入し理科教育の充実を図る
大正11年 学制頒布50周年記念式典を行う 保護者児童参列 県の学制頒布50周年式典で県下優良小学校の中に選ばれ表彰される
大正13年 学習文庫を設け国語教育の充実を図る(保護者からの寄付1086円85銭)大正期は特に学習器財の活用に力を入れ郡内でも特色のある学校経営が成された
昭和 元年 教育方針 知育 算術読み方の成績向上に努める 訓育 神社掃除 敬神崇祖に努める 作業訓練毎月13日年男子藁作業 女子ぞうきん作り 体育 学校体操連合体操 徒競走 綱引き 運動会 遠足等の工場に努める
昭和 4年 児童数の増加により校舎増築 二階建て四教室を本館裏に増築する 害虫駆除をして受賞菌3円を牧口農会から受ける 蛆蠅駆除で受賞金5円を牧口農会から
受ける
昭和 6年 牧口小学校同窓会創立される
昭和 8年 緒方郷体操・唱歌視察会開催される 教育製作展覧会が大分市で開かれ成績優秀(牧口村・模型・洋画、習字、手芸、手工芸) 緒方郷連合運動会が開かれ、本
校が最高点を取る 郡教育会主催農園視察会が行われ、施設、経営とも優秀と認められる 校舎改築、講堂新築落成式が行われる 近代的な木造建築で郡内一
といわれ、校歌に「木の香新たに・・・」と歌われている
昭和 9年 郡教育会主催主席訓導会が開かれる 豊岡知事外100名が来校し教育内容の優秀さが認められる 緒方郷主催図画講習会が開かれ30名来校 男子師範学校
先生の指導を受ける 緒方郷主催習字講習会が開かれ男子師範学校の先生の指導を受ける
昭和10年 県教育会主催学童展で図画・習字が多数入選する 広瀬神社鎮座祭、郡体競技会に多数上位入賞し県体にも3名入場する 三重農学校運動会には、男子優勝、
女子4位 又郡体操祭競技会にも男女とも器械使用優勝 男子水平跳び、女子前後開脚跳び、共に優勝する(競技会では応援歌で応援した)
昭和13年 肝油ドロップを使用するようになる。
昭和14年 当時の教育努力点 実力向上をめざし 毎月末能率調査 地区別成績グラフ図示 体位の向上をめざして 懸垂・歩法の訓練 非常時清新訓練 毎月一日・十五日神社参拝 将士感謝 武運長久祈願 毎月十日 合同訓練、生活指導、隔月 慰問文発送 毎月 廃品回収 平均売り上げ20円 このころは中休みには歩行
訓練を続け、5月5日の児童愛護の日には遠足(登山遠足)で体を鍛えていた 勤労奉仕、5年生以上は、出征兵士の家庭に出掛け、麦刈りや田植え、稲刈りの加
勢をする。(その間、上級生から鎌や鍬の使い方など技術を学ぶ一方体の鍛練や奉仕の心を身につけた)5年生以上徒歩で竹田広瀬神社参拝 その他相撲大会
や体育大会、運動会で体を鍛える
昭和15年 紀元2600年記念開墾作業(5年生以上)祝賀式の後、学級別に村内の神社(宇田社、平岡社、琴平社、日吉社、鹿島社)を参拝する
昭和16年 部落賞を出す(金5円を国防献金をする班)雨堤、宗像班 廃品回収(金3円を国防献金する班)下天神 長畑班 (当時子牛1頭の値段が5円程度であった)
牧口国民学校となる
昭和17年 国民学校修了式順序1一同着席 2一同敬礼 3開式の辞 4国歌奉唱 5勅語奉読 6勅語奉答唱歌 7学事報告 8修了証書授与 9修業証書授与 賞状授与
学校長晦告 来賓祝辞 修了生総代答辞 父兄謝辞 修了生唱歌 修業生唱歌 閉式の辞 一同礼
昭和18年 郡指定体育衛生研究会が開かれる 昭和18年度中出征兵士見送り34回 英霊出迎え10回 鼓笛隊を編成し牧口駅頭にて盛大に兵士を戦場に送る この頃か
ら17歳前後の少年兵や女子挺身隊の壮行も行われた
昭和19年 学校教育経営方針 1皇国の道に則り国民の基礎的鍛錬 2教科研究 3皇運扶翼の魂の育成 尽忠報公 4体練衛生教育の重視 5科学教育 6銃後後援教育(勤労奉仕・兵士歓送・英霊出迎・慰問文) 7職業指導教育 8戦力増強教育(食料増産・荒れ地開墾・軍用免・各供出物) 9防空訓練設備 戦争が厳しくなり、国
民全体が不自由な生活を余儀なくされ「欲しがりません。勝つまでは」が合い言葉であった
昭和20年 家庭教育指定村に裁定される 修業式で受賞すべき者 1実践力旺盛な者2創造性顕著な者 3責任感旺盛な者 4体力向上に努力した者 5一ヶ年ー八ヶ年皆
勤した者 高等科生徒は、飛行場作りや勤労奉仕、防空壕堀に終日従事する 8月までの四ヶ月の空襲警報回数88回を数える 校庭は、いも畑になり学校周囲
にはたくさんの防空壕が掘られる 学と結成される 軍隊の予備軍的存在で勤労動員など進んで行う 村葬6柱(戦死者の葬儀)
昭和20年 終戦 農繁休暇(麦刈り・田植え・稲刈りなど農繁期に3日~7日学校を休みにして家庭の農作業を加勢する)初めて進駐軍来校(学校では戦争に関する生類を隠す)
昭和21年 天長節(天皇誕生日)儀式挙行する 甘藷を生産し非農家の児童に販売する(食糧難続く)
昭和22年 各部落毎に学芸会をする 校庭の忠魂碑・日露戦没記念碑を撤去する 新制中学校が設立される(義務制になる)牧口国民学校が廃止され牧口小学校となる
PTA結成される(学年PTA・学校PTA・部落PTA)
昭和23年 ミルク給食始まる 6年生修学旅行開始(一泊二日別府方面)コア・カリキュラム研究会が開かれ郡内から300名の先生方参加する(教科の枠を解き生活経験を
中心に各教科を位置づけた教育課程) サマータイム実施される (夏の間始業時間を早め、学習や仕事の能率を上げようとする取り組み)チフス予防注射 5・6
年生少女歌劇鑑賞に緒方まで出掛ける ナトコ映画鑑賞
昭和24年 合川小中学校と合同体育祭をする
昭和25年 郡社会科(新しい教科)研究会を本校で開催する 井戸(玄関横・講堂裏)の綱の取替 開校記念日祝賀会を行う
昭和26年 郡指定PTA研究会が開かれる
昭和27年 ピアノを購入し音楽教育に力を入れる 全校女子シラミ駆除を行う
昭和28年 大野直入珠算競技大会でAチーム優勝する
昭和29年 大野郡指定国語研究発表会に郡内約100名の先生が参加する
昭和30年 町村合併により校名が清川村立北小学校になる
昭和31年 県指定理科研究発表会が開かれる
昭和32年 海水浴(4年生以上黒島か日吉原に、一泊二日で行く)
昭和34年 五社連合祭(御供に児童が出るため授業半日で打ち切る)
昭和38年 県指定図工科研究発表会で多数の先生が参加する
昭和39年 PTA作業で鉄棒・石運び・図書修理などをする
昭和42年 校旗・校歌制定式が行われる(校区民の寄付による)
昭和43年 輪転機購入する
昭和46年 図書室にテレビ用フィルダー線を配置し視聴覚機器のよる教育の充実を図る昭和47年 共同調理場の完成により完全給食始まる スポーツ少年団結成(野球・剣
道・卓球)
昭和48年 新校舎落成式が行われる。
昭和52年 体育館落成する(総工費40607000円)(内容設備は寄付金による)昭和53年 県指定習字研究会が開かれる
昭和54年 学校林(前久保)に櫟450本を植林する 校舎裏の土手に躑躅400本を植林する
昭和57年 灯油保管庫を設置する
昭和59年 運動場西側に防球ネットを設置する
昭和60年 文部省指定「体力づくり」推進校になる 北小学校育成会発足(会費一戸年間300円会員数538戸)プール落成式が行われる(総工費368万円)文部省指定を契
機にアスレチック遊具、運動場の整備、運動用具の整備がPTA中心に行われる 文部省指定、体力つくり研究発表会(1年次)が多数の参加者の元で行われる
昭和61年 開校100周年実行委員会立ち上げる 一輪車10台寄贈(レクレーション協会)祝100周年秋季大運動会 テーマ「きびきび」大運動会 体力つくり研究発表会(2 年次)県内から200名の先生方参加のもとに盛大に行われる 記念碑校門の脇に建立
昭和61年 開校100周年記念式典挙行される 記念碑除幕式・餅まき・記念式典・神楽・祝賀会 400名ほどの参加
昭和62年 新春親子三代遊び大会 校区内史跡めぐり競歩大会
平成 2年 5年生教室の床の張り替え工事完了 祖父母学級の参加者60名に達する 全校餅つき大会(PTA)の加勢による)
平成 3年 校舎外壁コンクリート崩落防止の工事完了 大野郡音楽祭に4年生参加する平成 4年 この頃学校では集会活動が盛んになり学年を解いた「縦割り集会」が行われる(内容は草取り・縄跳び・リズムなど)
平成 5年 プールシャワーを設置する 焼却炉改修(ダイオキシン対策の一環として)学校週五日制についてのアンケート集約 新春遊び大会(ウォークラリー)をする
平成 6年 科教室にテレビを配置し視聴覚教育の充実を図る 家庭科調理台二機設置する
平成 7年 隔週土曜日休業となる(週休の過渡期措置として)学校土曜日休業についてのアンケート集約 1・2・3年生生活科学習で学校周辺の野外学習をする コピー機(
印刷機設置)設置 教材用倉庫を校舎裏に建てる(村労評の事務所を移転する) 電話機(ファックス付き)設置する 元教育長から図書券(10万円 )贈呈される エアコン(職員室・図書室)設置 調理台を理科室に設置し家庭科教室と兼用で使用する 北小学校子ども祭り(縦割り班ごとに遊びを企画立案する)パソコン1台設置される 1・2年生テラス屋根張替
平成 8年 体育館雨漏り修理 全校井崎キャンプ
平成 9年 薩摩芋栽培(1年生-4年生)稲の栽培(5年生-6年生)を総合学習とし行う 11月収穫祭をする 校舎も雨漏りを防ぐために屋上に屋根を付ける 国旗掲揚台ポール設置 校長室の壁、廊下張替 親子ふれあいの会で餅つきをする
平成10年 フレッシュランド水泳教室 プール全面塗装工事をする
平成11年 パソコン5台導入される 校舎裏側側溝工事をする 国際交流を始める(国際交流員の活用)
平成12年 障害児学級を設置する 県指定ボランティア協力校になり福祉センターとの連携を図る
平成13年 インターネット接続なる 5年生を中心にみつば苑との交流を盛んにする 県PTA公開研究発表会を参加者300名で盛大にする 各学年とも教育機器を駆使した発表をし好評を得る
平成14年 小学校統合にともない校舎の大規模改修をする 北小学校閉校記念事業実行委員会が結成される
平成15年 本校舎裏に特別教室棟ができる フェンス・中央公民館への階段改修される
平成16年 閉校記念式典
戻る






